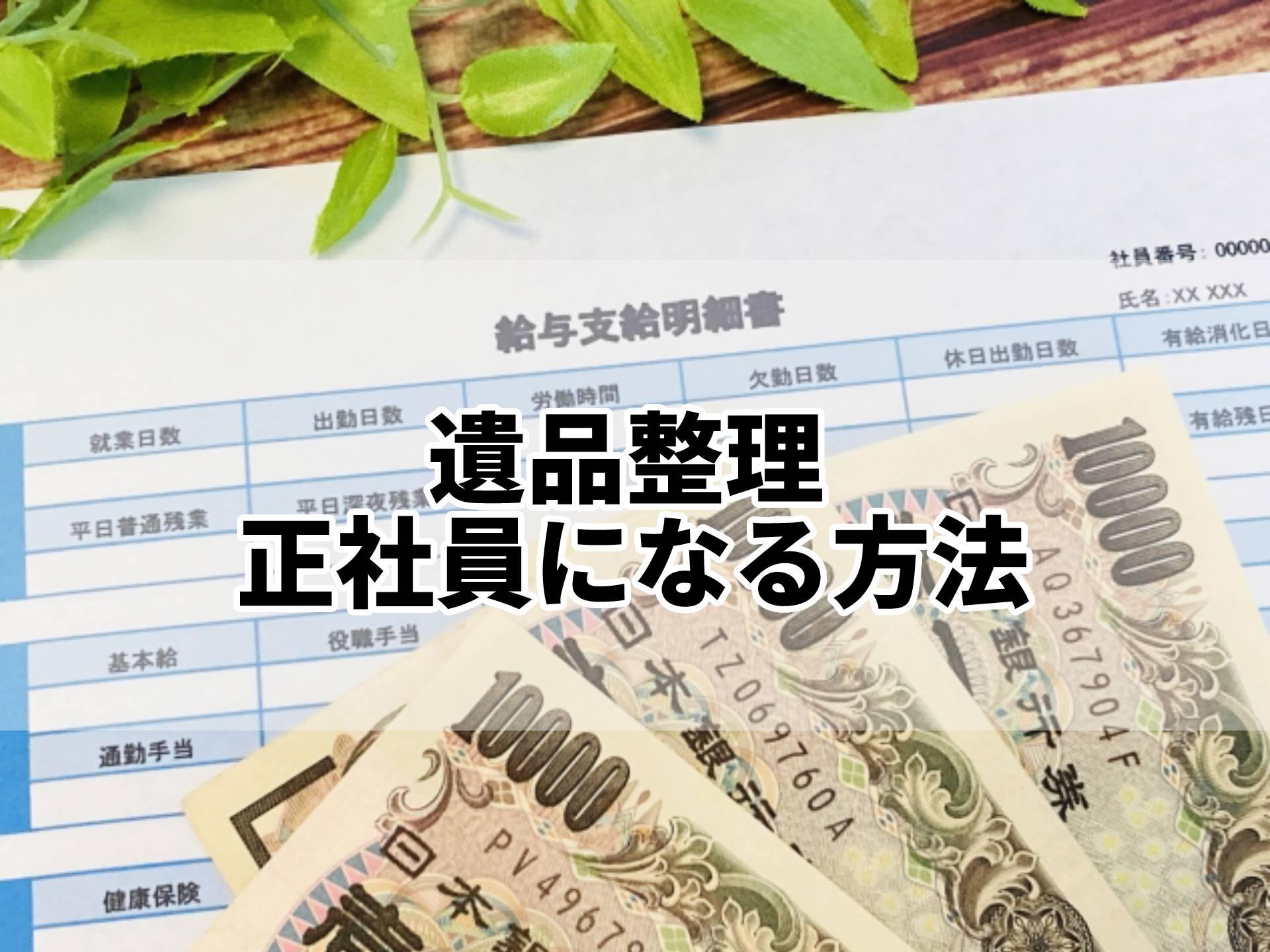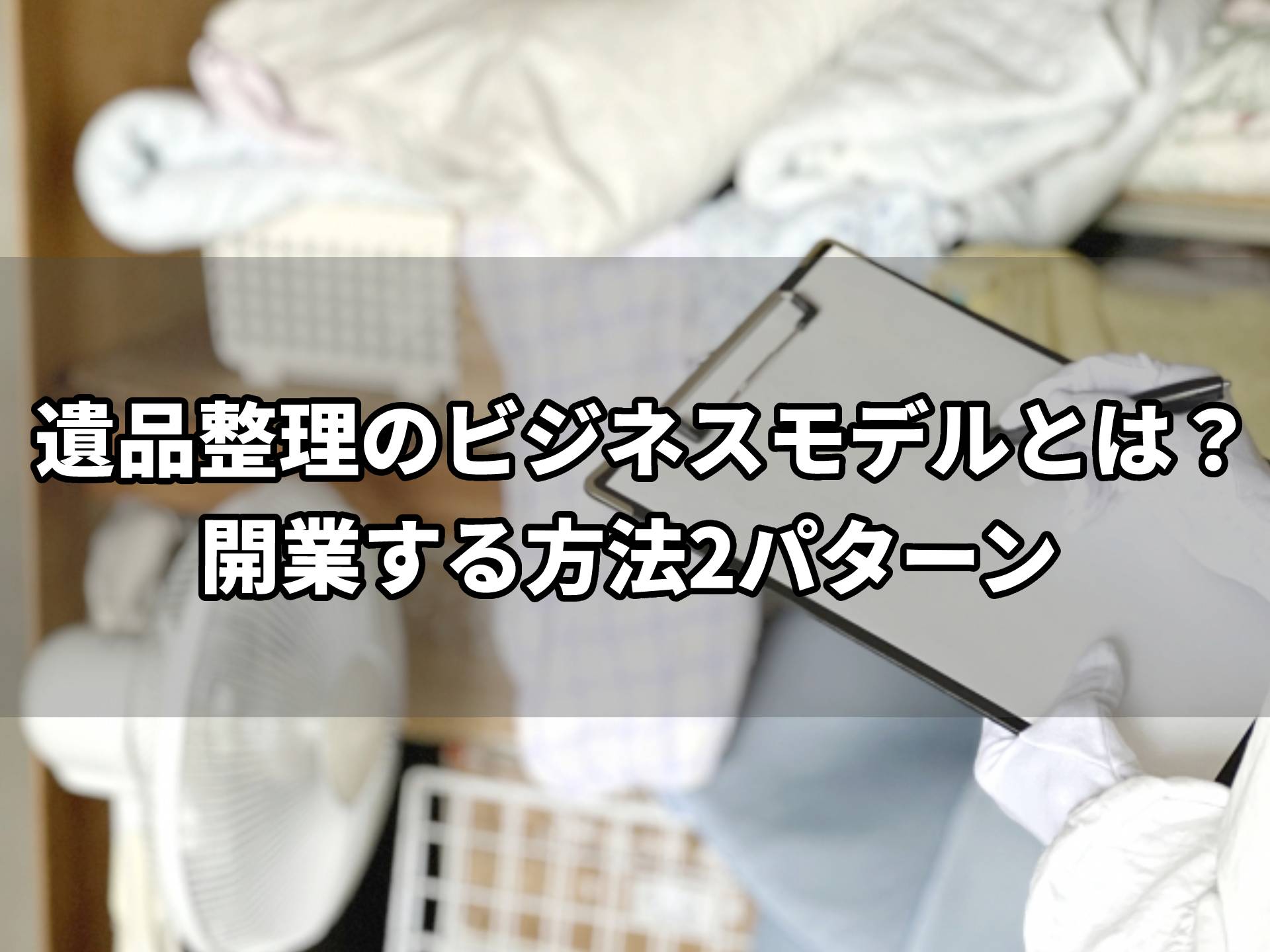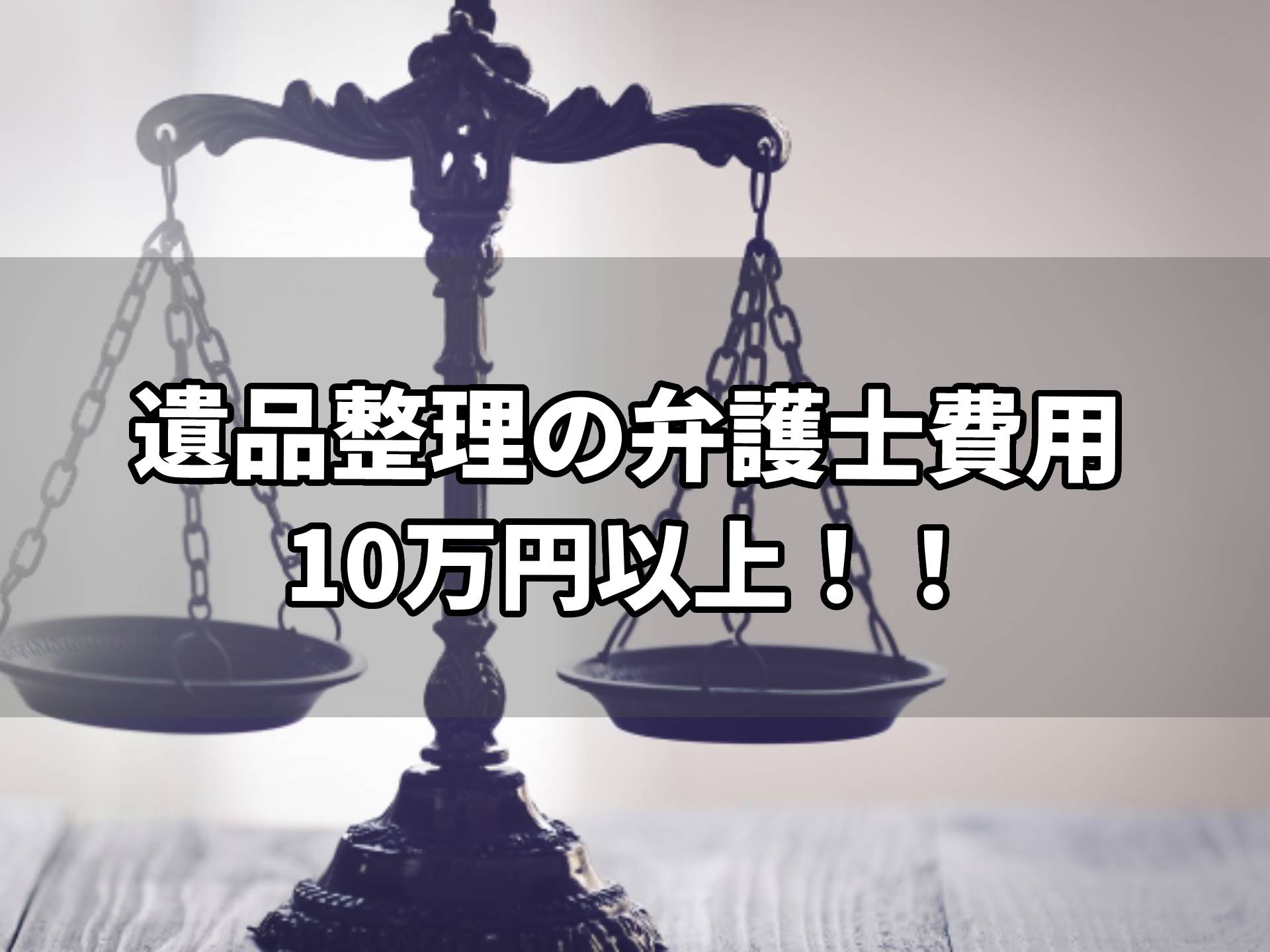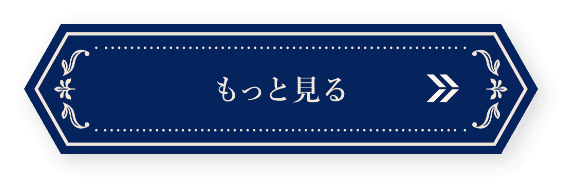遺品整理士は国家資格なの?実は遺品整理には2つの認定資格がある!
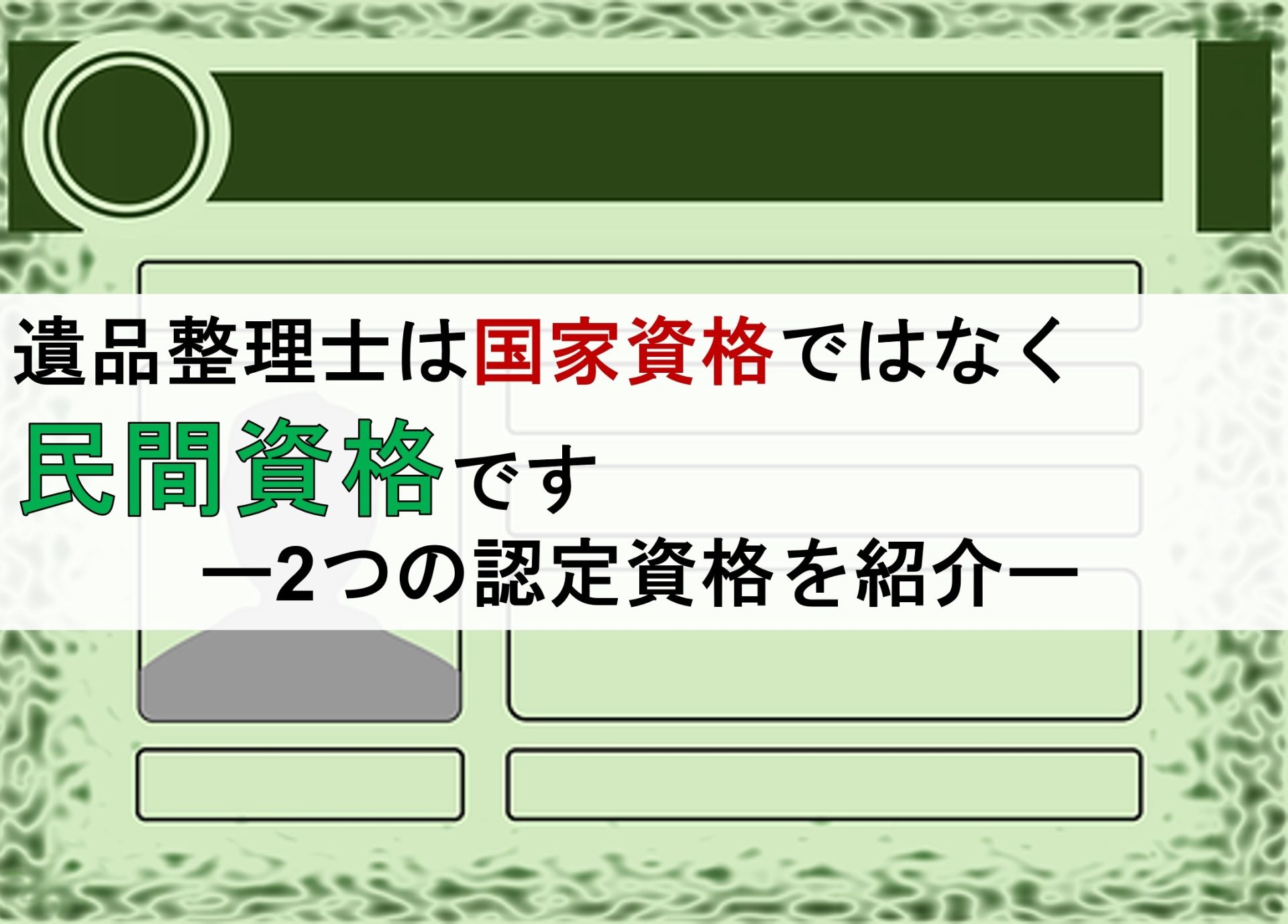
遺品整理士って「士」がついているから国家資格なの?
という事は難しいの?
遺品整理士は士業に分類されますが、弁護士や司法書士とは違い、遺品整理士認定協会が発行する「民間資格」になります。
そのため、有資格者のみが遺品整理事業に携わることができるというわけではないのです。
また、遺品整理士の他に「遺品整理アドバイザー」いった認定資格があるのもご存知ですか?
今回は遺品整理の専門家として取得できる認定資格について紹介していきたいと思います。
この記事を最後まで読むことで以下の悩みが解決できるでしょう。
| ・遺品整理の認定資格
・資格の取り方 ・試験の難易度 ・資格を取得するメリット ・遺品整理業で取得するべきその他の許可証 |
是非最後までご覧ください。
1:遺品整理には2つの認定資格がある

「遺品整理の専門家」として取得できる資格は2つあります。
- 遺品整理士
- 遺品整理アドバイザー
どちらも国家資格ではなく、社会的需要に伴いできた「民間資格」なので、遺品整理業を行う上で必須というわけではありません。
しかし、この2つの認定資格をも取得していれば、遺品整理士として信頼され、遺品整理業を行う上で必ず役に立つでしょう。
1-1:遺品整理士
遺品整理士は「一般社団法人遺品整理士認定協会」が発行している民間資格です。
遺品整理業界の発展・健全化、依頼者の利益の保護を目的として作られました。
遺品整理の資格というと一般的にこちらの資格を指す場合が多いです。
遺品整理士
| 受講資格 | 誰でも受講可能 |
| 受講期間 | 2か月間(目安) |
| 受講料(入会金) | 25,000円 |
| 会費(認定手続き含む) | 10,000円(2年有効) |
遺品整理士は認定講座を受け、課題レポートを提出し、合格すれば認定証書を発行してもらえます。
遺品整理士の勉強内容や難易度はこのあと第2・3章で解説していきます。
1-2:遺品整理アドバイザー
遺品整理アドバイザーは「一般社団法人日本遺品整理協会」が発行している民間資格です。
遺品整理の普及と質の向上を目的として作られました。
主に遺品整理の基本知識とアドバイザーとしてのスタンスを学ぶことができます。
遺品整理アドバイザー
| 受講資格 | 誰でも受講可能 |
| 受講期間 | 4時間 |
| 受講料 | 22,000円(教材、認定料含む) |
| 会費(任意入会) |
認定会員:入会金10,000円+永久会費12,000円 認定法人会員:入会金60,000円+永久会費60,000円 |
こちらは全1回の講座とレポート・アンケート提出をすれば認定証書を発行してもらえます。
この「遺品整理アドバイザー」を取得し協会員に登録すると、「プロフェッショナル認定講座」を受講することができます。
プロフェッショナル育成コース
| 受講資格 | 遺品整理業を生業にする人
遺品整理アドバイザーを取得している 協会員である事 |
| 受講期間 | 6日 |
| 受講料 | 70,000円 |
こちらのコースでは以下の事が学べます。
- 遺品整理における契約内容
- 遺品整理における労務態勢
- 不動産及びリサイクルに付随するもの
- 営業方法(情報発信/SNS活用術、動画サイトいついて)
- 特殊清掃法
- 価値あるものと値打ちのあるものの違い
- 模擬ルームにて実践練習
- 各業種専門家セミナー参加資格
- (社労士、弁護士、FP、不動産、葬儀、墓石、骨董、リサイクル、廃棄処分屋)
- その他
2:遺品整理士の合格率は3人に1人

遺品整理士の合格率は65%となっています。
口座を受講してレポートを提出すればOKというわけでなく、毎回3人に1人のペースで不合格者が出ています。
基本的には配布される以下の教本の内容を講座で学び、問題集に沿って課題レポートを作成するといった流れになります。
- 遺品整理とは何か
- 専門家が今、必要とされる理由とは
- 取り巻いている、様々な社会問題
- 実務を行っていく上で必要なこととは
- 行われている”実際の業務”とは
- 作業を行う上での留意点
- 法規制との関わりについて
- 事例研究について
3:遺品整理士の業務内容
では遺品整理士は具体的にどのような仕事をしているのでしょうか?
「遺品整理サービス」というと、現在では特殊清掃や不動産管理、行政手続きなどの業務も含まれていることが多いですが、ここでは基本的な遺品整理の業務内容を4つに分けて解説していきます。
3-1:遺品の仕分け
まずは遺品の仕分けを行っていきます。
基本的には以下のジャンルで仕分けを行います。
- 故人の契約や個人情報などに関する重要書類・重要物
- レンタル品・定期購入品
- 形見分けする遺品
- 買取可能な遺品
- 廃棄する遺品
遺品の仕分けは遺品整理の肝ともいえる作業であり、遺族と話し合いながら慎重に丁寧に進めていく必要があります。
遺品整理業の中でも「遺品を勝手に捨てられた」といったトラブルが多発しているので、注意が必要です。
3-2:不用品の回収
仕分けが終わったら、不用品と判断したものはトラックに運んで廃棄またはリサイクルをします。
運搬作業になるので、いかに手際よく作業を進められるかが肝心です。
また、不用品とはいえ遺品を供養することになるので丁寧な扱いを心がけてください。
廃棄には「一般廃棄物収集運搬許可証」「産業廃棄物収集運搬許可」が必要で、リサイクルには「古物商許可証」が必要になってきます。
必要な許可証については第4章で解説をします。
3-3:遺品整理後の清掃
搬出作業が終わり、部屋の中が空っぽになってもそこで終わりではありません。
最後に簡単な清掃を忘れないでください。
故人と遺族に敬意を払って、部屋をキレイな状態にして遺品整理を終えましょう。
4:その他遺品整理に必要な許可証
近年では遺品整理の需要増加に伴い、遺品整理サービスの幅も広がってきました。
遺品整理業に伴い、必要になる許可証を紹介していきます。
4-1:一般廃棄物収集運搬許可証
遺品整理業者が一般の家庭から遺品を引き取る際に必要になります。
この許可証が無ければ、不用品や一般廃棄物を回収することができません。
ただし、許可証を持って居る業者に「委託」する場合は、許可証を持っていなくても大丈夫です。
一般廃棄物収集運搬許可証は各都道府県の市区町村の許可が必要になってきます。
東京23区の場合は「東京二十三区清掃協議会事業調整課許可係」が窓口となっています。
4-2:産業廃棄物収集運搬許可証
「一般廃棄物収集運搬許可証」が一般的な家庭から排出されるゴミの回収です。
事業活動によって排出される廃棄物の回収が「産業廃棄物収集運搬許可証」です。
飲食店で不要となった冷蔵庫などはこの「産業廃棄物」に分類されます。
「一般」と「産業」を混同しないよう注意しましょう。
4-3:古物商許可証
業者が中古品(古物)の売買を行うには「古物商許可証」が必要です。
つまり遺品整理業者が遺品の買取サービスを行う際はこの許可証が必要不可欠になってくるのです。
古物商許可証は各都道府県の公安委員会に申請することで取得できます。
まとめ
以上、遺品整理の資格について紹介しました。
遺品整理の認定資格を取得すると
遺品整理業者で働く人⇒給料UP
遺品整理事業を始める人⇒信頼性があがり、依頼が増える
といったメリットがあります。
年々、遺品整理業者は増えてきており、競争も激化しているので、これから遺品整理の仕事を始めたいという方はできれば取得することをおすすめします。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。