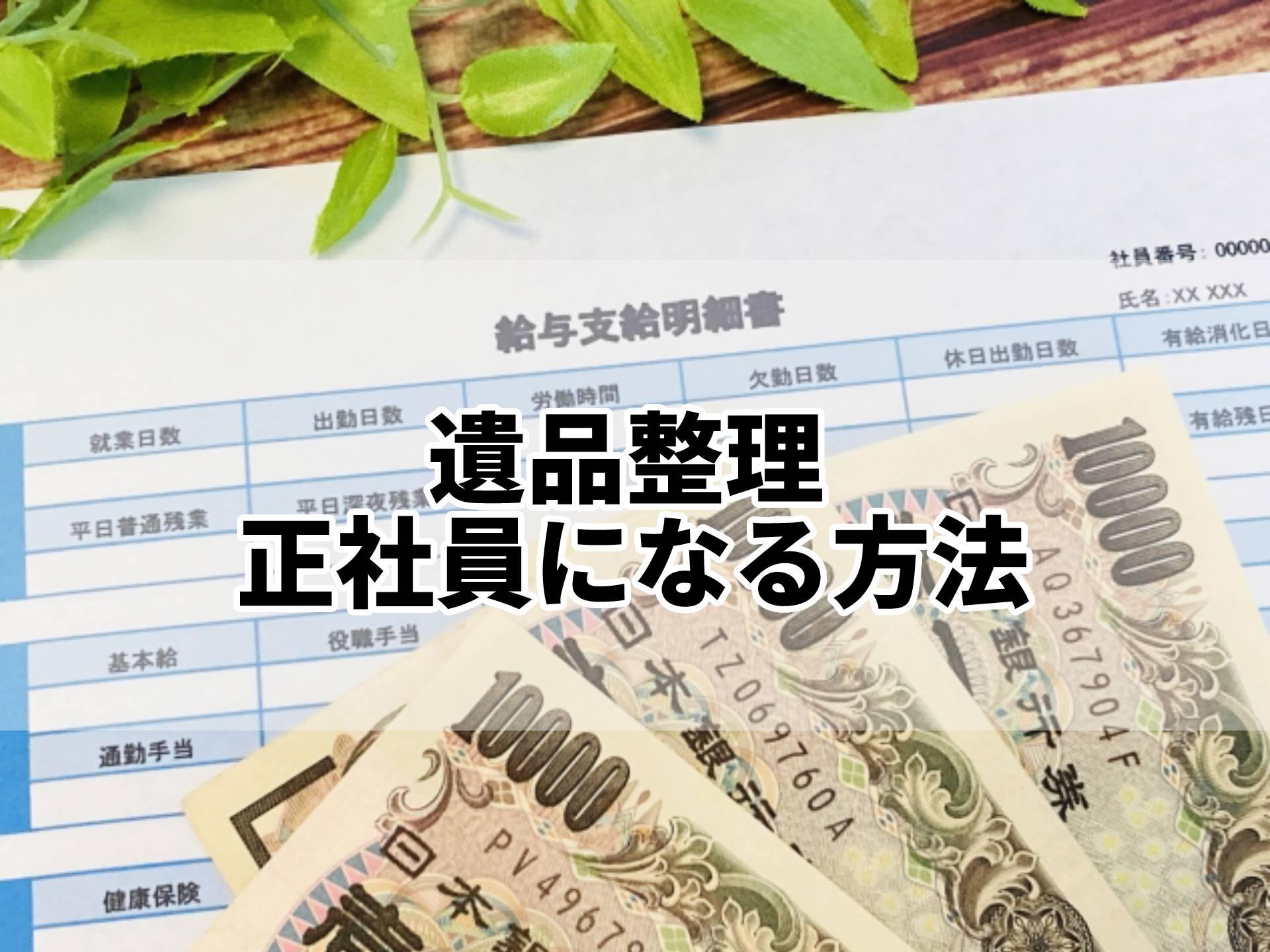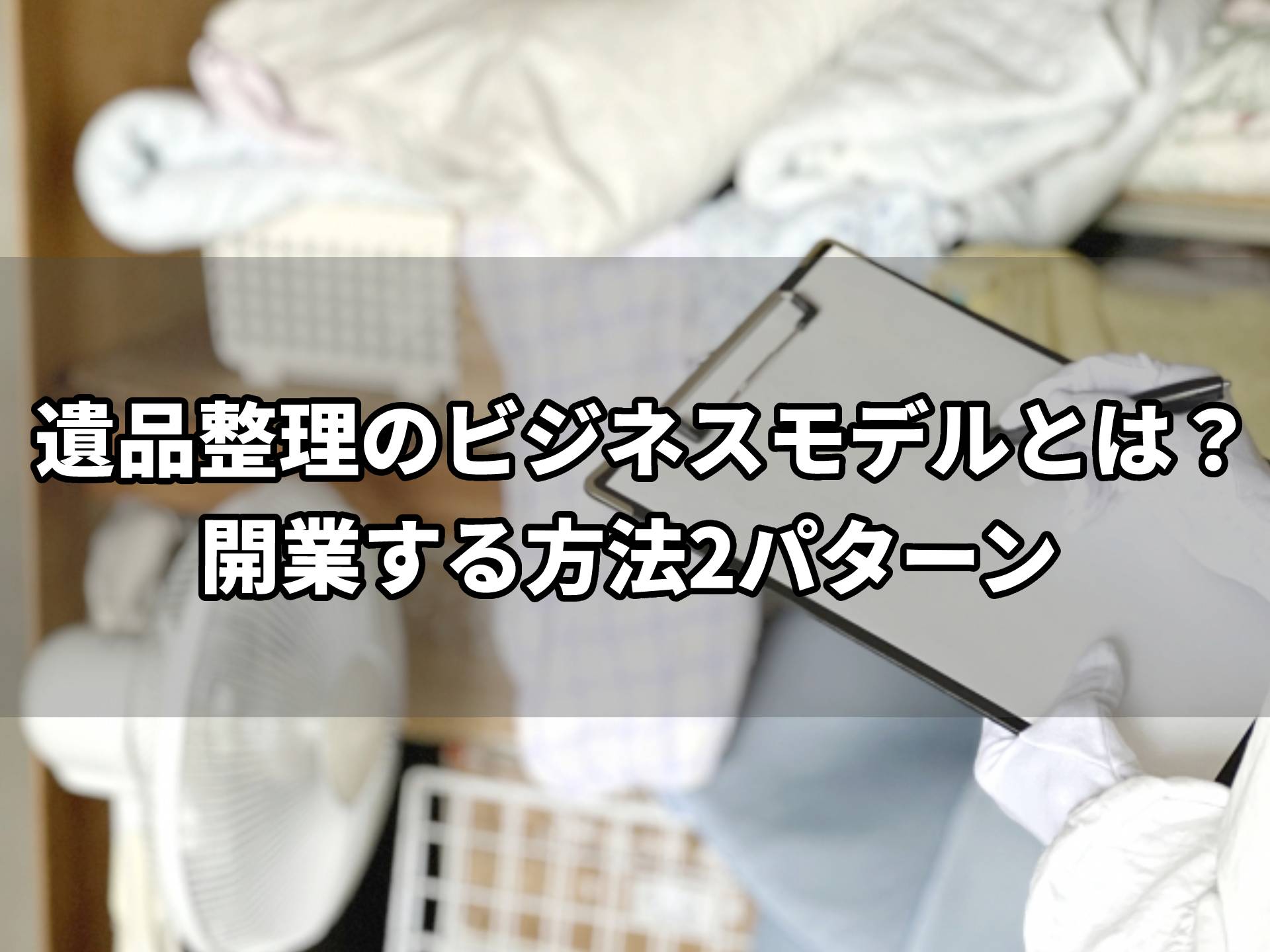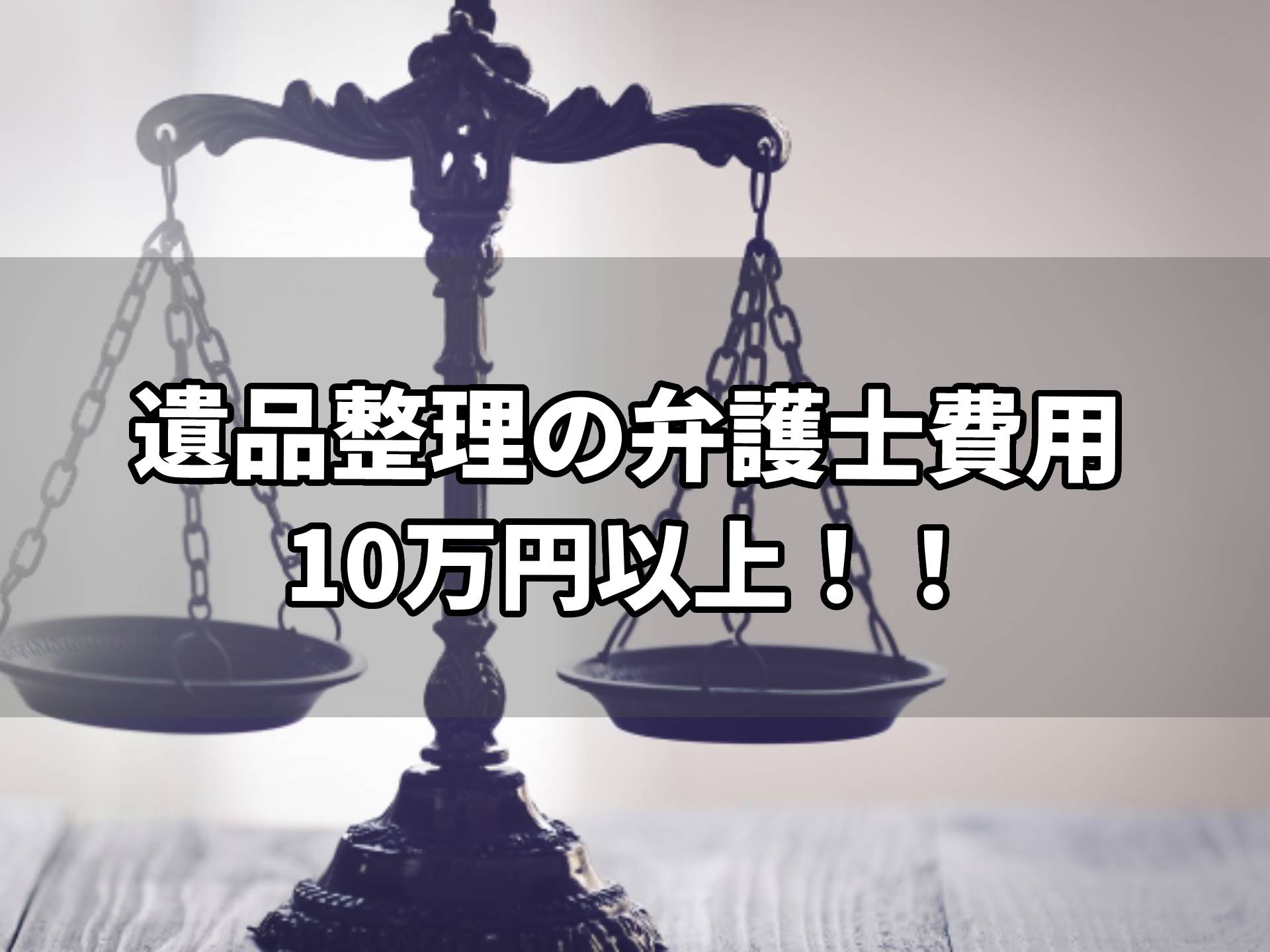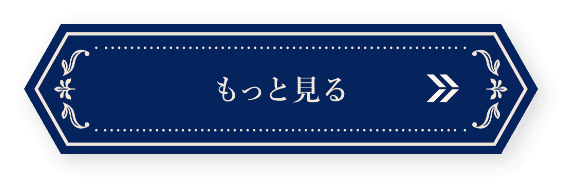遺品整理業の市場規模は拡大し続ける|売上5000億円越えの注目事業

遺品整理事業の市場が急速に拡大していることはご存知ですか?
現在の遺品整理業の市場規模は5000億円以上といわれています。
これには少子化問題や出生・死亡者数などの社会問題が背景としてあります。
最近では、某経営者の「日本はいずれ消滅する」といった発言でも話題になりましたね。
遺品整理を題材とした韓国ドラマも制作されるほど、遺品整理は注目度の高い事業の1つと言えるでしょう。
- 遺品整理の市場規模
- なぜ需要が増加しているのか
- 遺品整理の内容とトラブル事例
今回は遺品整理業の市場規模と、その要因について解説していきます。
是非最後までご覧ください。
1:拡大し続ける遺品整理の市場規模

2021年3月に総務省が実施した遺品整理サービスの現状調査によると、対象69業者のうち、52業者が平成21年以降にサービスを開始していることが報告されています。
また、遺品整理士認定協会が2018年に発表した、約8000の加盟業者の年間売り上げは5000億以上にも上ります。
遺品整理業者はハウスクリーニングやリサイクルショップなどの関連サービスに取り組んでいるため、それらの事業の市場規模も参考にしてみてください。
関連事業の市場規模はこのようになっています。
| 建設 | 57兆円 |
| トラック運送業 | 15.8兆円 |
| リユース事業 | 2.4兆円 |
| 葬祭 | 1.8兆円 |
| 便利屋 | 1兆円 |
| ハウスクリーニング業 | 3500億円 |
| 廃棄物処理事業 | 2200億 |
2:なぜ急速に拡大しているのか【遺品整理の実態】

では、なぜ遺品整理サービスがここまで急速に拡大を続けているのか。
それは主に高齢化社会による空き家増加などの理由により、遺品整理の需要が高まっていることが最大の要因と考えられるでしょう。
▼少子高齢化
総人口及び総人口に占める0~14歳、65歳以上の割合の推移
| 総人口 | 0~14歳 | 65歳以上 | |
| 平成元年 | 1.231億人 | 18.8% | 11.6% |
| 平成9年 | 1.264億人 | 15.3% | 15.7% |
| 平成30年 | 1.265億人 | 12.2% | 28.1% |
| 令和3年 | 1.254億人 | 11.8% | 28.8% |
※参照元:総務省統計局
日本人口のピークは平成20年にピークを迎え翌年からは減少傾向にあります。
平成9年には65歳以上の割合が15歳未満の割合を上回りました。
また、国立社会保障・人口問題研究所が2017年に発表した「日本の将来推計人口」によると、2053年に1億人を割って2065年には8,808万人になるものと推計されています。
|
2021年の出生・死亡数 |
|
| 出生数 | 842,897人 |
| 死亡数 | 1,452,289人 |
※厚生労働省統計情報参照
また、2021年時点で死亡数が出生数を大幅に上回っており、出生数は統計開始以降最小、死者数は戦後最多を記録しました。
厚生労働省の「人口動態統計」によると、死亡数の推移は2040年で168万ともいわれています。
出生数の増加と死亡数の減少による人口減少の解決が課題としてある中、遺品整理サービスの需要はこれからも増加し続けるでしょう。
▼空き家問題
少子高齢化が加速する一方で、日本人の平均寿命は延びたことにより、介護施設の利用が増加し、住居が空き家として残されることが多くなりました。
総務省の「住宅・土地統計調査」によると、全国の空き家は1988年から2018年の30年間で394万戸から849万戸となり、2倍以上も増加しています。
また、空き家は、固定資産税対策(所有している土地に住宅が残されていれば6分の1に減額)のために取り壊さず残しておくケースが多いため、今後ますます遺品整理の依頼は増加すると考えられます。
3:遺品整理業者って何をしているの?
そもそも何から何までが遺品整理サービスなのでしょうか。
実は遺品整理は産業として特定の分類に含まれているわけでもなければ業法があるわけでもありません。
つまり明確にはよくわからないのです。
遺品整理には主に以下のような5つの仕事内容があります。
- 遺品の仕分け・処分・捜索
- 遺品の搬出作業
- 遺品の買取
- 遺品整理後の清掃
- デジタル遺品整理
これらの内容については「遺品整理に資格は不要!遺品整理に関係する資格と仕事内容を大公開」で詳しく紹介しているのでよかったら参照してください。
▼遺品の仕分け・処分・捜索
故人が残した遺品を仕分け・捜索をして処分をします。
遺品整理の基本的な業務なります。
▼遺品の搬出
遺品の仕分けが完了したら、次は遺品を運び出します。
こちらも遺品整理の基本的な業務になります。
▼遺品買取
遺品の買取には古物商許可証が必要です。
そのため遺品買取を実施していない業者もあります。
▼ハウスクリーニング
孤独死などで残った体液や異臭を完全に除去する場合には、特殊清掃が必要です。
▼デジタル遺品整理
故人の情報が入っているデジタル製品の情報を整理・消去します。
4:遺品整理のトラブル事例を3つ紹介

遺品整理の急速な需要増加に伴い競争が激化し、遺品整理業者と消費者間でのトラブルが多発しています。
遺品整理でのトラブルは主に契約トラブルとなっています。
トラブル事例①:契約を急かす
トラブル事例②:不当な追加料金の請求
トラブル事例③:遺品を勝手に処分する
トラブル事例①:契約を急かす
契約を急かすこと自体は違法ではありませんが、それでも消費者に考える時間を与えなければ悪質業者として認識されるでしょう。
また、事実でない事を理由に契約を急かした場合、消費者契約法に違反します。
虚偽申告による契約は、不利益事実の告知となり、消費者契約法に基づき契約を取り消すことができます。
「既に10件の問い合わせが入っているから」という具体的なウソをついた場合は完全にNGですので虚偽申告には注意してください。
トラブル事例②:不当な追加料金の請求
「想定していた以上に時間がかかった」などの理由で追加請求をすることも消費者の利益を損害することになります。
想定をしっかりしていないのに作業を始めた時点で業者に落ち度があります。
遺品整理を依頼されたら、必ず現場調査をして作業内容や作業時間が記載された正確な見積書を作成してください。
そして消費者が見積り内容に納得したら、成し見積書の内容と差異がないようきっちりとした契約書を作ましょう。
最悪の場合損害賠償を請求されるので注意してください。
トラブル事例③:遺品を勝手に処分する
遺品を勝手に処分すると「器物損壊罪」で訴えられ、損害賠償を請求される可能性があります。
また、故意的でなかったとしても「業務上過失」として罪に問われます。
事前に処分内容を記載した見積書を提出していたとしても、遺品整理を始めるまえに、遺族に同意または同意書の確認を行ってください。
出来れば同意書を作成して遺族の方にサインをしてもらうと安心して作業を進めることができるでしょう。
まとめ
遺品整理は少子高齢化により、急速に市場規模が拡大している事業です。
その反面、競争が激化し無理な契約をすすめるといったトラブルも増大しています。
現在、遺品整理事業を規制する法律がないため、遺品整理業者には法令順守や消費者の利益を守るといったマナーが強く求められるでしょう。
遺品整理事業に新規参入を考えている方は、必要許可証や関連法令などを事前に必ず確認しておきましょう。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。