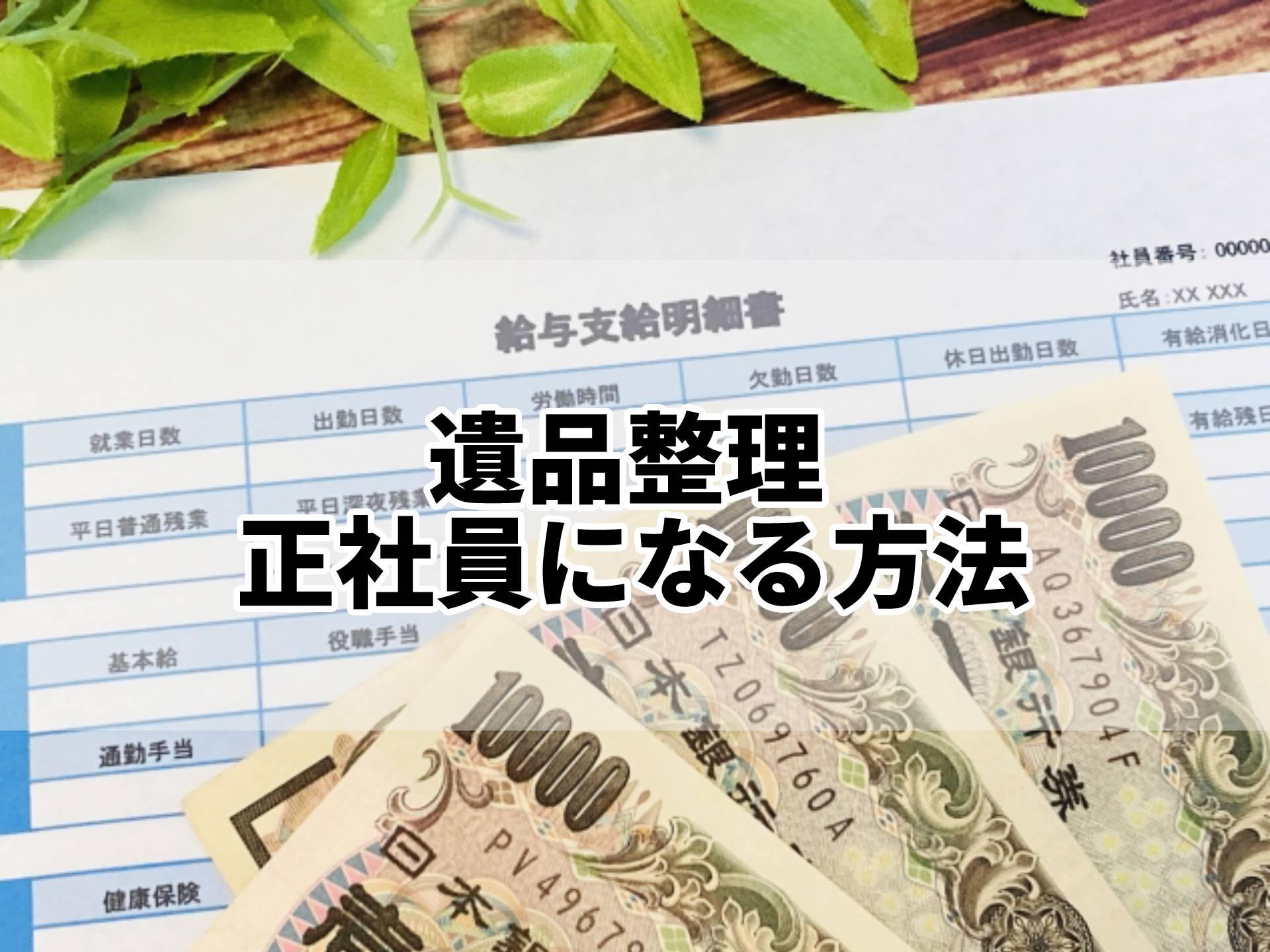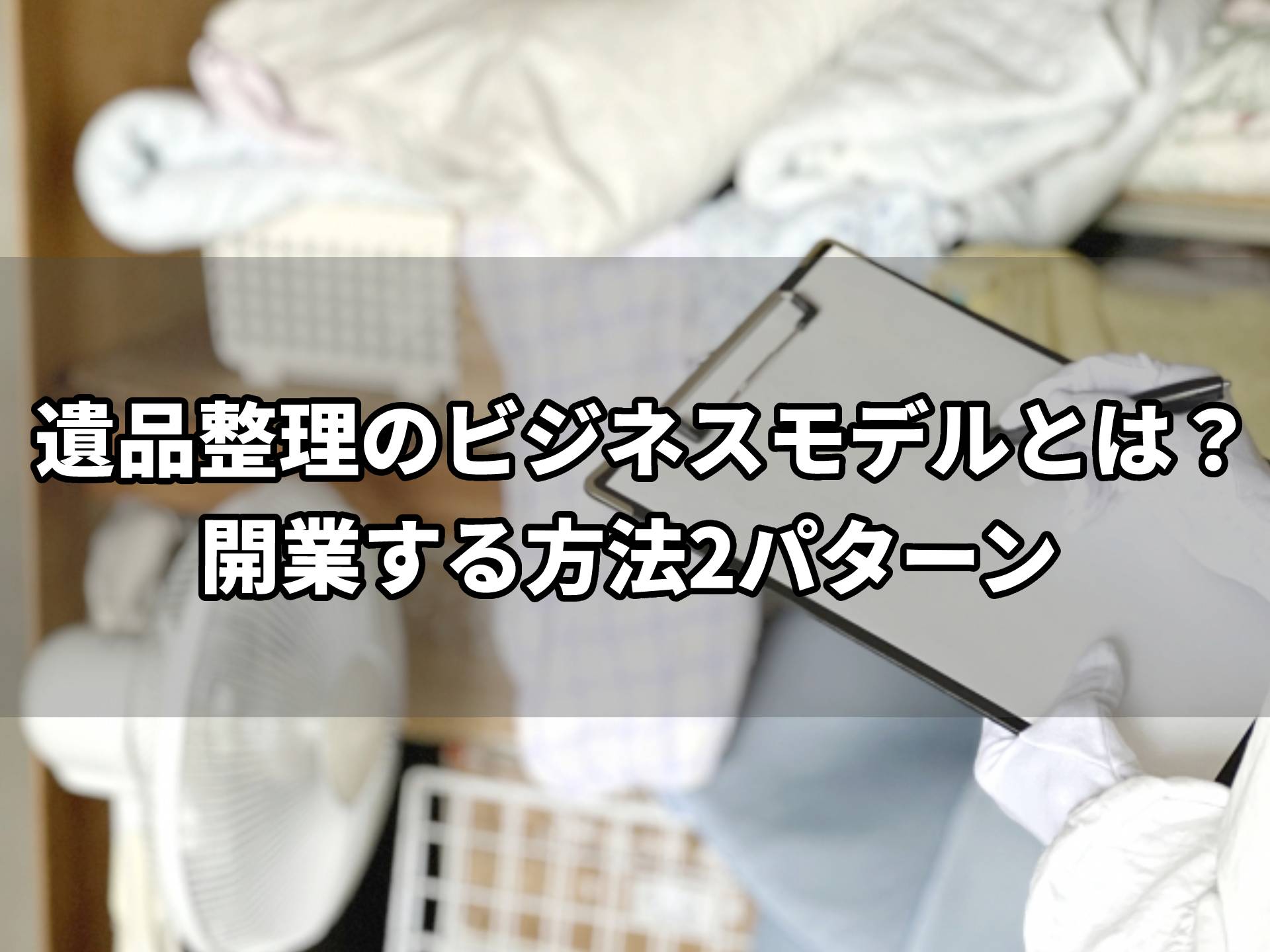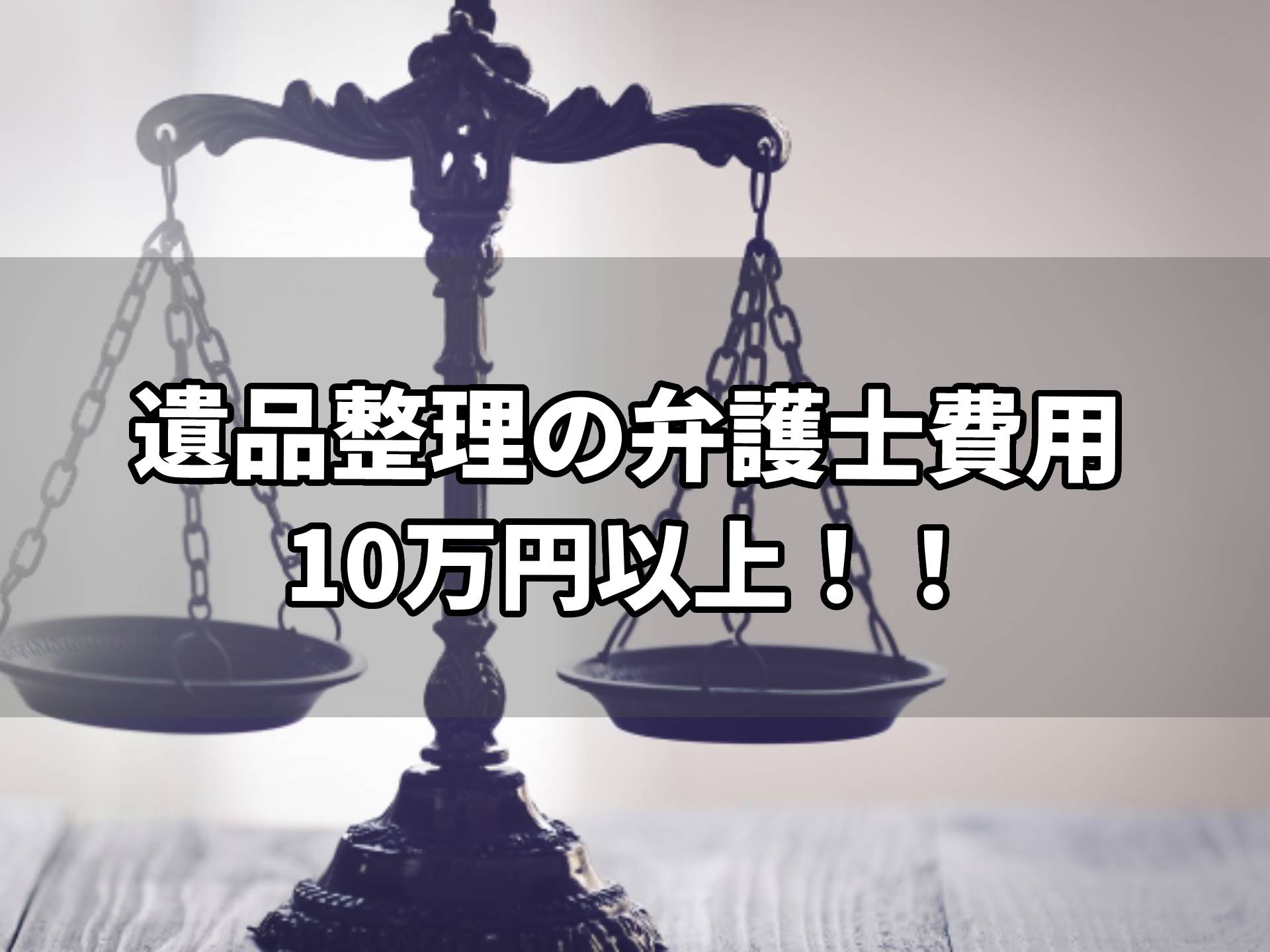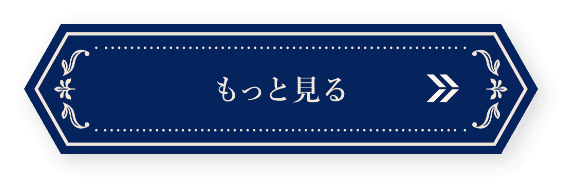遺品整理の契約書って?|7つの注目ポイントと見積書との関係
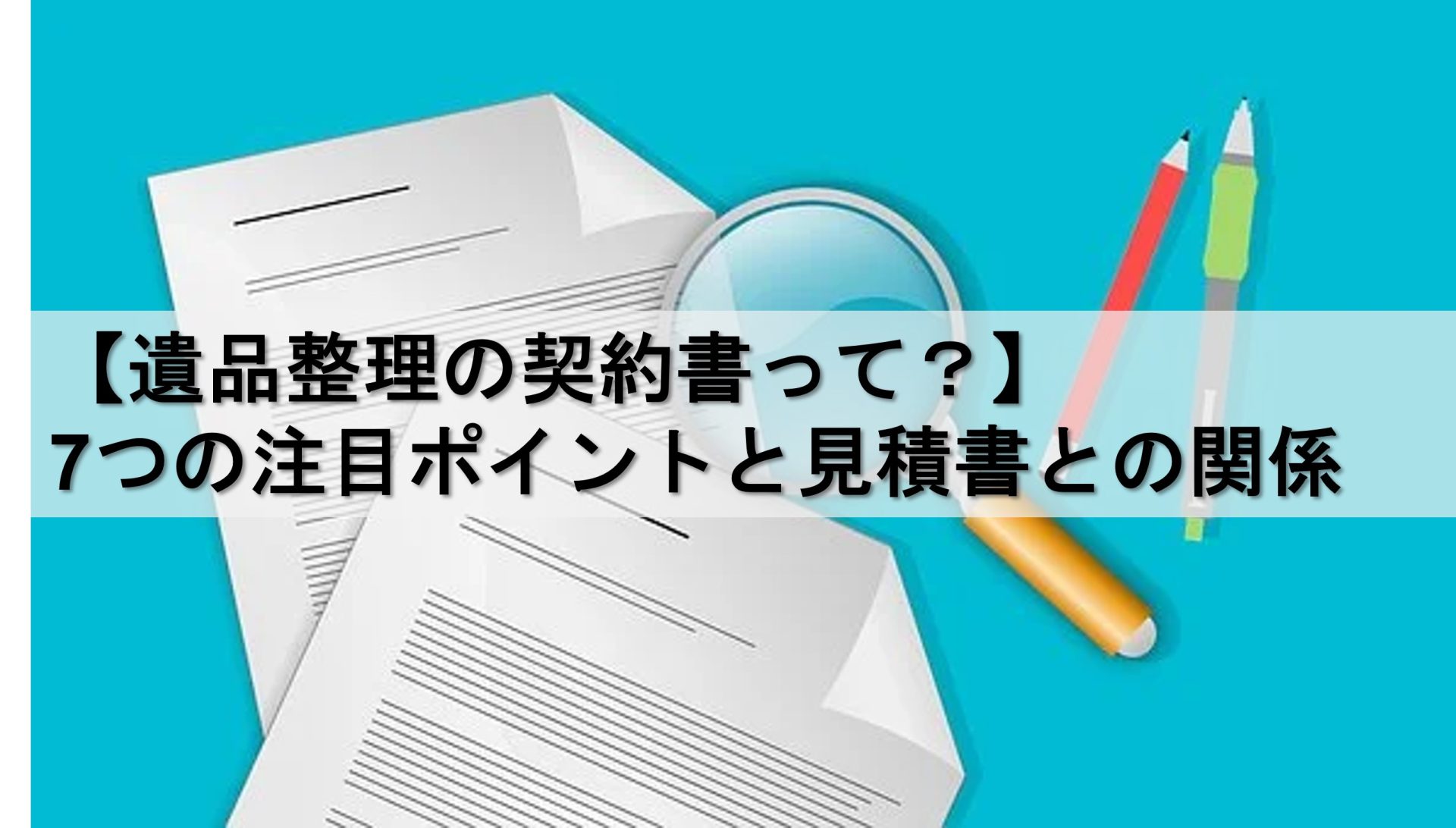
遺品整理を依頼したら契約書はもらえるのでしょうか?
確かに業者によっては契約書を作成していない場合がありますが、きちんとした遺品整理業者であれば契約書を作成して作業前日に契約を結びます。
契約書は遺品整理を円滑に安全に進めるために重要な書類です。
けど、契約書に書いてあることってなんだか小難しいイメージがありますよね。
不憫な契約を結んでしまわない為にも、この記事では契約書の内容をすこし噛み砕いて、抑えるべきポイントをいくつか紹介していきます。
- 遺品整理の契約書で注意する7つのポイント
- 契約書と見積書の違い
- 同意書は必要?【目的と注意点】
- 遺品整理に関する契約書の実態
また、同じく重要な書類である同意書や見積り書にもついてもご案内していきますので、ぜひ最後までご覧ください。
1:遺品整理の契約書で注意する7つのポイント

契約書の目的は、業者と依頼者の間で約束したことに間違いがないか、サービス内容や料金に納得して、作業を進めてもいいか判断する重要な書類です。
遺品整理をする際に、自分が損をする契約を結んでいないか確認して、安全で円滑な遺品整理ができるように、7つのポイントに注目して契約書の内容をみていきましょう。
ポイント①:契約書の目的
契約書とは、相互の意思が統一されているかを証明する事が目的で作成される文書のことです。
つまり、一度契約書にサインをしてしまうと相互の意思表示が合致したことに承諾したことになり、あとから錯誤や内容の誤りに気付いても、契約を解除することは難しくなってきます。
優良業者に依頼しても、錯誤がある状態で契約を結んでしまっては結果的に依頼者が損をする可能性があります。
契約書に目を通して疑問に思う点や、意味がわからないことがあれば、遠慮なく業者に確認を取りましょう。
ポイント②:業務内容やサービスに関して錯誤がないか
遺品整理を始める前に、業者は依頼者か希望されているサービスや作業をもとに、実際に現場に伺い、現場状況をみて、遺品整理当日の作業内容を確認します。
作業の段取りが決まれば、業務内容や希望サービス、作業内容などの詳細が記載された見積書を依頼人に提出します。
そしてこの見積書の内容と契約書の内容が同一のものであるかを業者に必ず確認してください。
悪質な業者やいい加減な業者は見積りで約束したことを契約書に盛り込んでいない可能性があります。
業務内容やサービスは必ず見積書と照らし合わせながら目を通すようにしましょう。
ポイント③:記載されている対価に誤りがないか
遺品整理の対価として支払う金額が見積り書にて納得した値が記載されているか確認してください。
契約書を作る段階で、依頼者が変更を希望しない限りは見積書の内容が変わることはありません。
ポイント④:個人情報の秘密・保護に関して記載されているか
個人情報の秘密・保護を徹底することは企業が守るべき義務です。
これらの記載がなければまずその業者の利用は止めた方がいいでしょう。
ポイント⑤:理由により業務遂行できなかった場合の記載があるか
業者側の理由により業務遂行されなった時、あなたは業者に対して信頼感を失うかもしれません。
契約書の規定外事項について記載されているか確認してください。
この条項は、契約書に定められていない規定外の事項で問題が発生した場合に、「信義誠実の原則」を定めた内容なります。
つまり、業者が予定通りに業務を履行しなかった場合に、信頼を裏切らないように、相当の理由や再履行の計画を説明して、約束を守ることを伝えなければなりません。
これは依頼者の理由により遺品整理が中断または中止になっても同じことが言えます。
悪質な業者は契約不履行など関係なしに、依頼者から逃れようとするので、契約を交わす際にはこの規定外事項についても事前に業者側に確認をとっておきましょう。
ポイント⑥:記載条項が依頼者にとって不利にならないか
依頼者にとって不利な条項というのは、わかりやすい例でいうと
「甲(業者側)が判断した時」といった、業者側の判断ベースで契約の解除や対価の減額などを一方的に行える内容は、依頼者にとって不利になるので注意してください。
業者側の都合で支払い方法が変更されて支払いが遅れたにも関わらず、契約不履行として違約金を支払わされても、納得いきませんよね?
客観的に判断されなければ条件が緩くなり、不利な条項となりえるので注意してください。
契約の有利不利はとても難しい問題なので、複雑な状況に直面したときは法律の専門家に相談することをおすすめします。
ポイント⑦:免責事項が記載されているか
免責事項について予め知っておくことで悪質な業者に言いくるめられることを防ぎます。
免責事項は、一定の事由により生じた債務不履行を免責するという条項のことですが、状況によっては依頼者にとって有利にも不利にも働きます。
依頼者が対価を期日までに支払わなかった場合、業者側は依頼者に責任を問うことができますが、不測の事態が起こったときはその責任を免れることができます。
つまりこの事項では、問題が起きた場合の責任を負う範囲の線引きをしています。
そしてこの線引きは業者側が都合よくしていいわけではありません。
免責事項の内容に疑問があれば、業者に必ず確認をしましょう。
それでも腑に落ちなければ、法律の専門家に無料相談で整合性を確認するのも1つの手段です。
2:契約書と見積り書の違い

見積書だけではダメなの?と疑問に思うかもしれません。
見積書⇒確認
契約書⇒合意
見積書には、遺品整理の日程や作業内容、見積り金額などの内容が記載されていますが、この時点で納得したとしてもまだ検討段階です。
最終的に、見積書の内容を含む契約書にサインをしてはじめて遺品整理が始まり、依頼者が対価を支払う義務が発生します。
3:同意書は必要?【目的と注意点】

同意書とは双方が同意したことを証明する書類です。
では、遺品整理における同意書とはなにか?
これは「故人の遺品を第三者が処分する」といった場合に遺族や親族が同意を証明する書類になります。
この同意書がなければ第三者が窃盗の罪に問われたり、相続トラブルが発生してしまう可能性があります。
ただし、この同意書は必ずしも用意しなくてはいけないものではありません。
遺族間で信頼していれば問題ありませんが、遺品整理業者などの第三者に依頼する場合には同意書を用意しておくと、後々トラブルが発生した場合に対処することができます。
同意書を作成する場合は、捨ててはダメなリストを載せておき、他の遺族全員のサインを記入してから遺品整理業者に提出しましょう。
4:遺品整理に関する契約書の実態

遺品整理サービスにおいて、業界を規制する業法がないために、契約トラブルなどの問題が多く発生しています。
2018年9月~2020年3月に総務省が69業者に行った調査では、24業者が契約書を交付していないという実態が浮かび上がりました。
24業者のうち17業者が必要性を感じないとの理由で契約書を作成しておらず、見積書と契約書をしていない業者は5業者でした。
5:しっかりした契約書を作成している遺品整理業者を選びましょう

遺品整理サービスの規制強化に関しては様々な視点から必要性を考えなければなりませんが、契約書の交付に関しては消費者にとって重要な問題です。
契約書を交付していない業者必ずしも悪質であるとは限りませんが、依頼者のリスクをできるだけ軽減するためにも、遺品整理を業者に依頼するときは契約書の交付の有無があるか確認しておきましょう。
まとめ
以上、遺品整理の契約書について紹介しました。
契約書というのは書いてある事が小難しく、法律的なことになると理解するのが大変です。
遺品整理を業者に依頼するときは、契約書の交付があるかを確認して、契約書の内容をしっかりと理解して、少しでも疑問や悩みがあれば必ず、業者や法律の専門家に確認することを忘れないようにしましょう
「とらのこ」では法令順守を徹底しながら遺品整理に取り組んでいます。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。