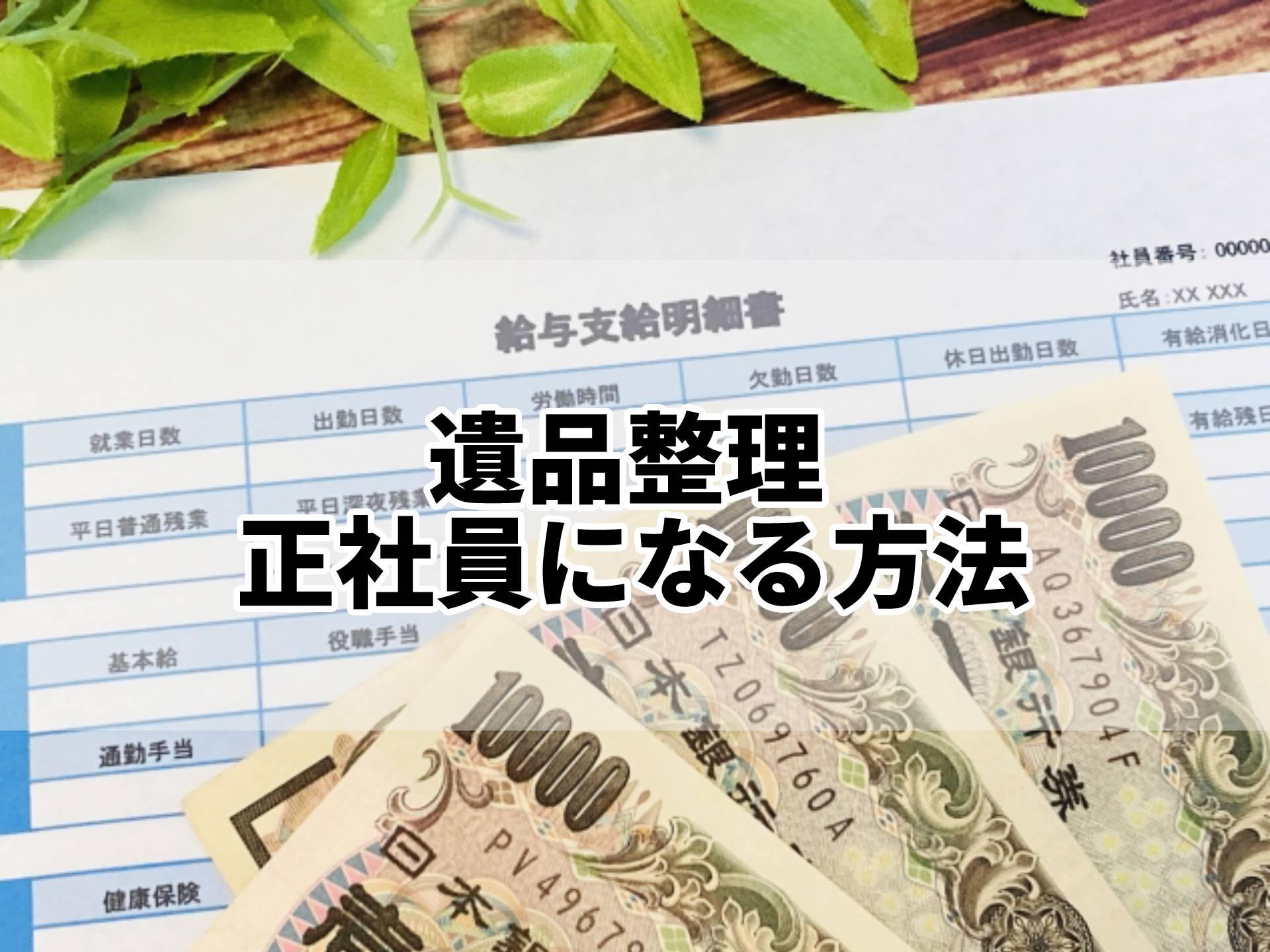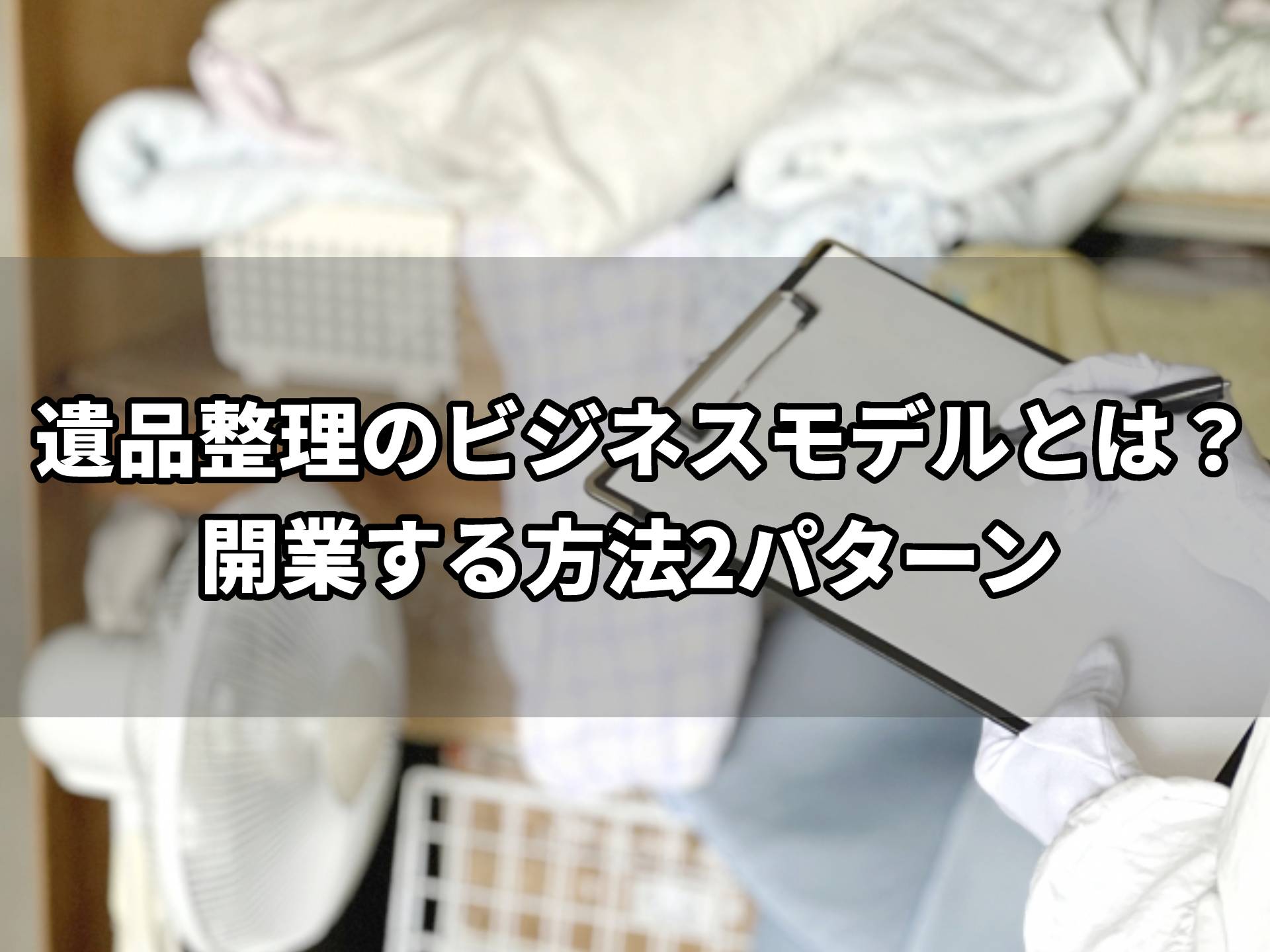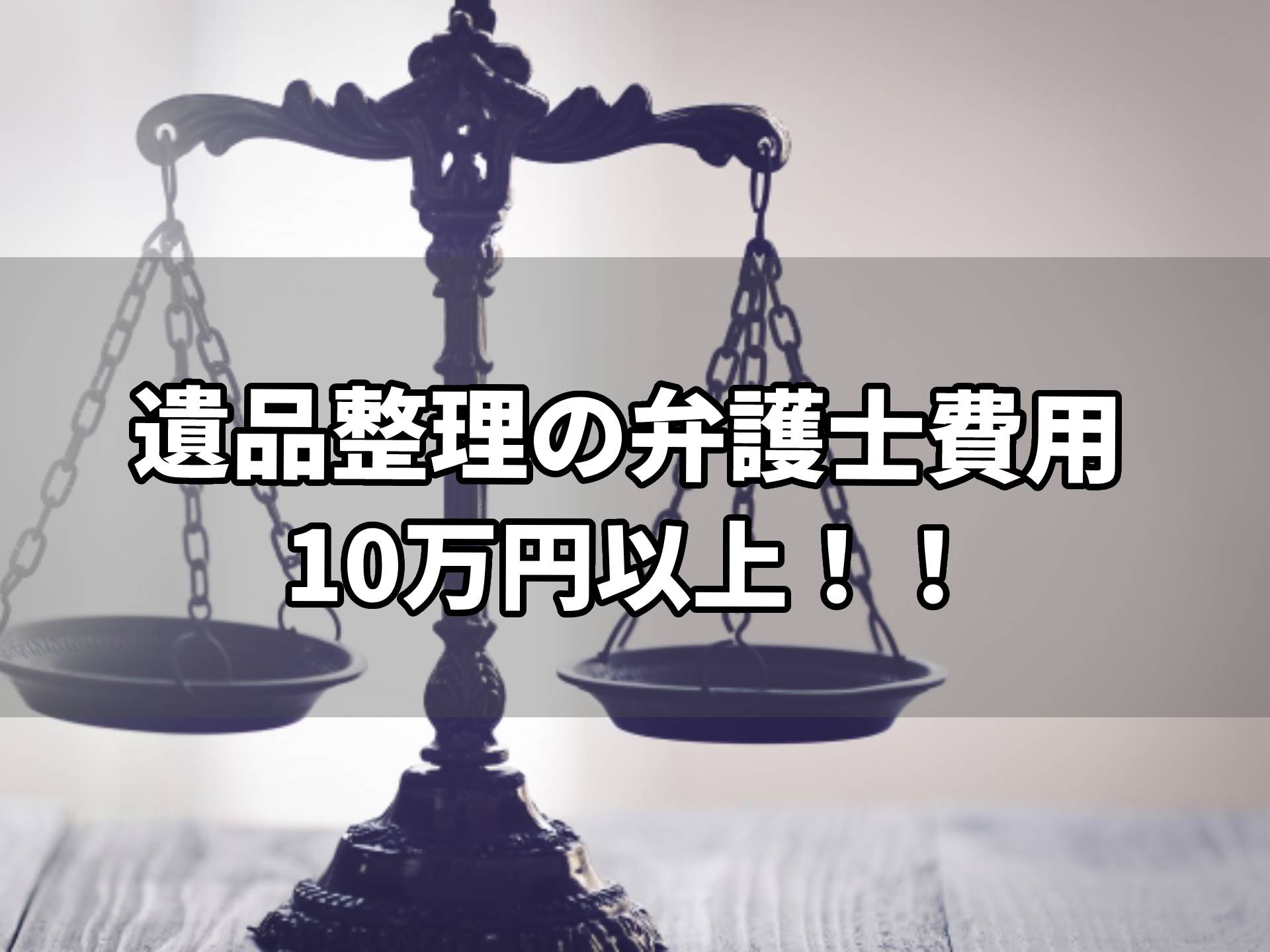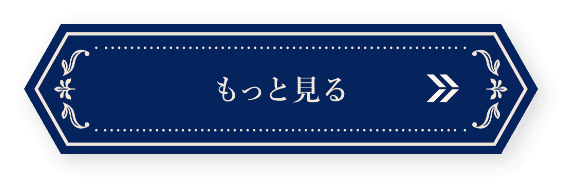【合格できる】遺品整理士になるためのレポートの書き方を伝授
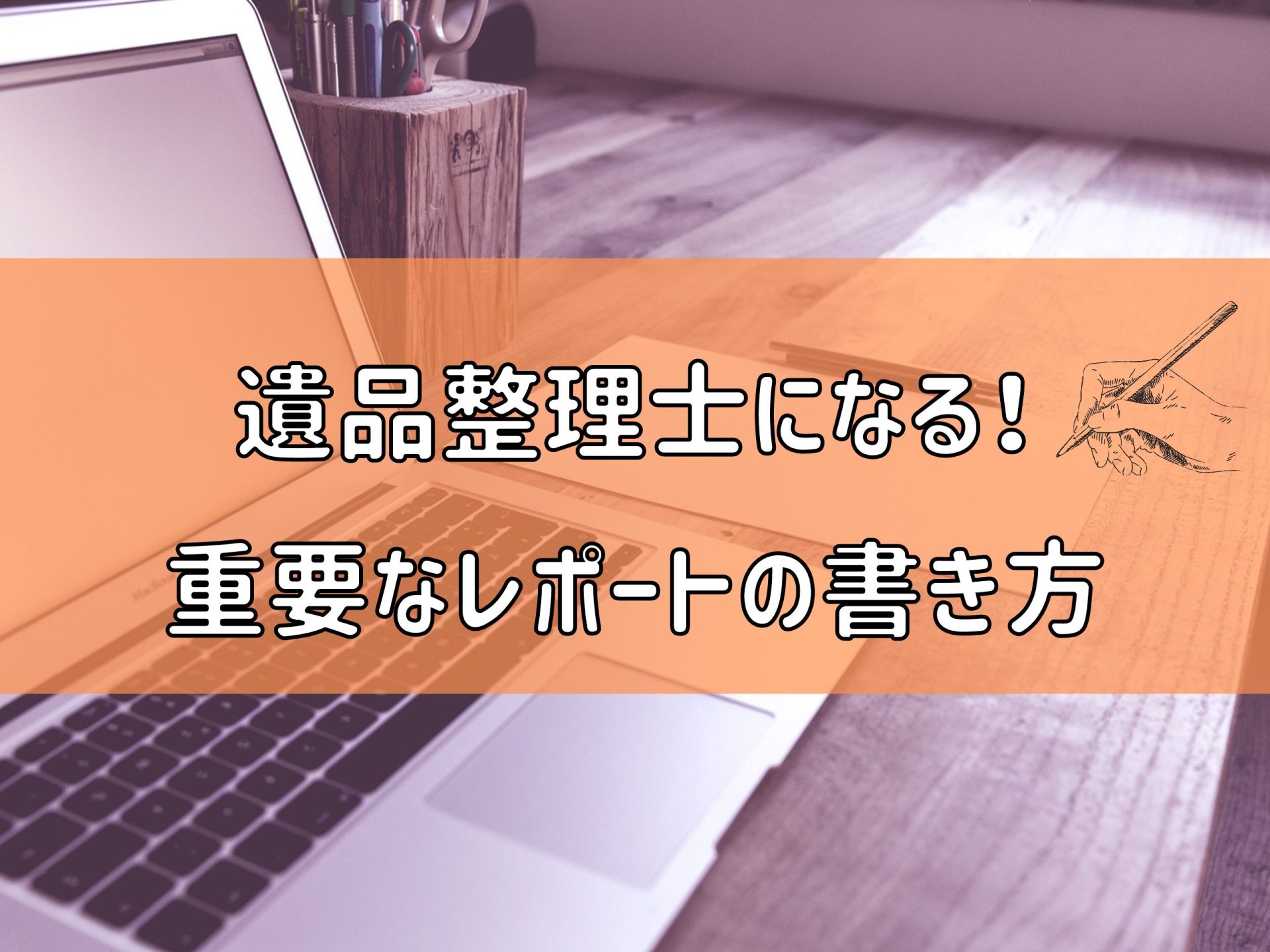
遺品整理士になりたい!
遺品整理士の資格を取得するために、必ず必要なのがレポートの提出です。
レポートを提出することにより、合否判定が出ます。
そこで、この記事では遺品整理士になるためにレポートの書き方などを解説していきましょう。
- レポートの書き方
- 遺品整理士になるメリット・デメリット
- 遺品整理士になるための費用
この記事を読んでいただければ、無事、遺品整理士になれることでしょう。
是非最後までご覧になって、参考にしていただければ幸いです。
1:遺品整理士の課題!レポートの書き方

遺品整理士とは遺品整理を仕事とする資格です。
遺品整理士は、一般社団法人遺品整理士認定協会が創設した資格となっており、般社団法人遺品整理士認定協会が実施する講座を受講し、課題レポートを提出して審査を通過した人のみが遺品整理士の資格を授与されることとなっています。
資格取得のための講義は、教本と資料集、DVDを利用した通信講座となっております。
すべての学習を自宅で完了させることができ、職を持つ人でも自分のペースで学習することが可能です。
講義に要する期間は2ヶ月間となっています。通信講座の内容は、「実際の作業手順」「具体例にもとづく事例研究」「遺品整理に関連する法律の解説」などで構成されています。
講師は遺品整理士・弁護士・大学教授などが担当しているため、遺品整理に関するあらゆる知識を実践ベースで学ぶことができます。
資格を取得するためのレポート
資格取得のために、1番肝心なのがレポートです。
遺品整理士のレポートで重要なことは、講義内容で伝えられた内容を正しく把握しておくことです。
レポートの内容は、そこまで難しいものではないため、正しい文章を確実に記述することができれば安心です。
講義を受けてわからないと感じた部分については、ノートを見返すなどをして内容を正しく理解しておきましょう。
講義の内容を把握できていれば、聞かれた内容からずれないように執筆をしていきましょう。
また、一般社団法人遺品整理士認定協会から、「只今、講座を申込み頂いた会員様からのレポートのご提出が相次いでおり、弊協会に200名様のレポートが殺到しております。もう少々お待ち頂けたらと思います。」との声明が出ています。
合否発表には時間がかかるということを把握しておくと良いかもしれません。
遺品整理士とは
先述もしましたが、遺品整理士とは、一般財団法人遺品整理士認定協会が認定している資格です。
資格取得後は、遺品整理の専門家として活躍することが可能です。
現在、遺品整理士は全国で20,000人以上おり、協会では、遺品整理業の開業のための支援も行っています。
遺品整理士の主な仕事内容は、必要品と不要品の仕分け・不用品の回収と適切な処理・家財の搬出・整理後の簡易清掃などとなっています。
2:知っておく!遺品整理士になるメリットとデメリット
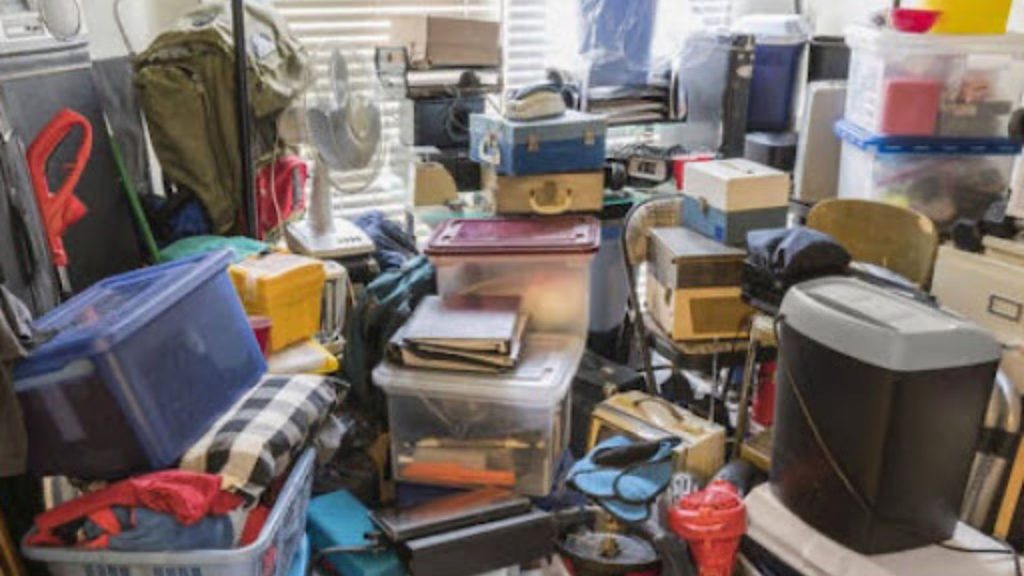
遺品整理士になる際に、メリット・デメリットを把握しておくことは重要ですので次を参照してみてください。
- メリット①:仕事の幅を広げられる
- メリット②:遺品整理士を名乗れる
- メリット③:就職しやすい
- デメリット①:責任を負う必要性
- デメリット②:正確な知識が必要
メリット・デメリットを確認して、遺品整理士の資格を取得するかどうか決めてみてはいかがでしょうか。
遺品整理士は、少子高齢化の進む日本で需要が高まりつつある職業の1つです。
遺品整理士の資格を持っていれば、これから就職に困ることはないでしょう。
それでは、3つのメリットと2つのデメリットを解説します。
メリット①:仕事の幅を広げられる
仕事の幅が広がることは重要です。
遺品整理のニーズは増大し続けていますので、遺品整理士はきわめて将来性のある資格といえます。
今の職を失ったとしても遺品整理士の資格を取得しておくことで、職を確保できますので取得しておいて損はないでしょう。
メリット②:遺品整理士を名乗れる
遺品整理士はだれでも名乗ることができると勘違いされがちですが、これは誤りです。
遺品整理士は遺品整理士認定協会だけが認定している資格であり、「遺品整理士」という名称も遺品整理士認定協会が創作したものとなっています。
そのため、資格を持たずに遺品整理士であることを名乗り、業務の宣伝などに使えば、遺品整理士認定協会から知的財産権の侵害で訴えられるという可能性があります。
つまり、遺品整理士の資格を持っている人だけが、この資格を名乗ることができ、自己の業務のために活用できるということです。
遺品整理士という名称を名乗れるということは、遺品整理の仕事をする人にとっては大きなアドバンテージとなります。
最大限に活用し、自分の仕事に活かしていきましょう。
メリット③:就職しやすい
遺品整理士の資格を持っていることで、遺品整理業の会社に採用されやすくなります。
また遺品整理業だけではなく、葬祭業や自治体の関連部署への採用度もアップします。
遺品整理に関する知識を持っているということは、葬祭業や自治体の福祉業務などにおいても即戦力となります。
遺品整理士の資格は意外なところでも役に立つのです。
デメリット①:責任を負う必要性
遺品の処分などを行うため、お客様の大切なものや貴重なものを壊してしまうと損害賠償などの話になりかねません。
細心の注意を払って仕事に取り組むようにしましょう。
デメリット②:正確な知識が必要
遺品の仕分けなどの仕事を始めとして、専門的な知識が必要な職業です。
曖昧な知識ではなく、専門的な知識が必要となりますのでしっかりと学習しておきましょう。
3:遺品整理士!資格取得にかかる費用

そのために必要な費用は、入会金の2万5000円、そして認定手続きを含む会費7000円です。
遺品整理士認定協会のサイト経由で受講の申し込みを行い、入会金を振り込むと問題集などが送られてきます。
レポートの提出を行い合格だった場合には、郵送されてくる合格通知を受け取ることができます。
しかし、合格通知を受け取ってすぐに遺品整理士として活動できるわけではありません。
認定手続きを行う必要があるのです。
顔写真などを添付した履歴書や同意書の返送を行い、会費を振り込みます。
手続きが完了してしばらくするとカードタイプの認定証と認定証書が送られてきますので受け取るようにしましょう。
まとめ
今回は遺品整理士の資格について解説しました。
この資格を取得することで仕事の幅が広がり将来も活躍することができる人材になれるでしょう。
また、最近では親族の遺品整理をするためにこの資格を取得する人もいるようです。
役立つ場面は多くありますので、この記事をきっかけに遺品整理士の資格取得を検討してみてください。
弊社ブランド買取とらのこは、遺品を出張買取しております。
遺品の処分でお困りでしたら、とらのこに気軽にご相談ください。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。