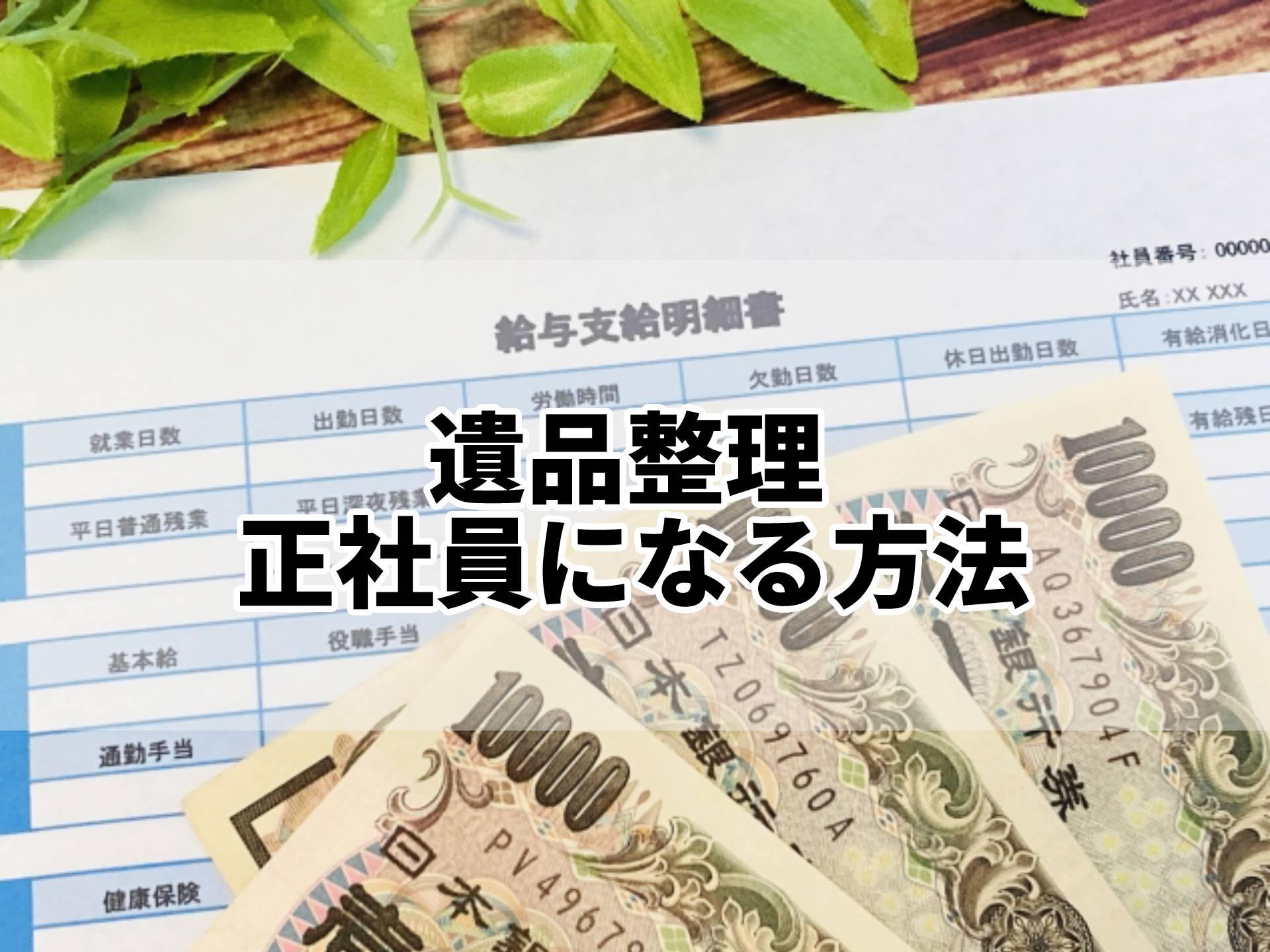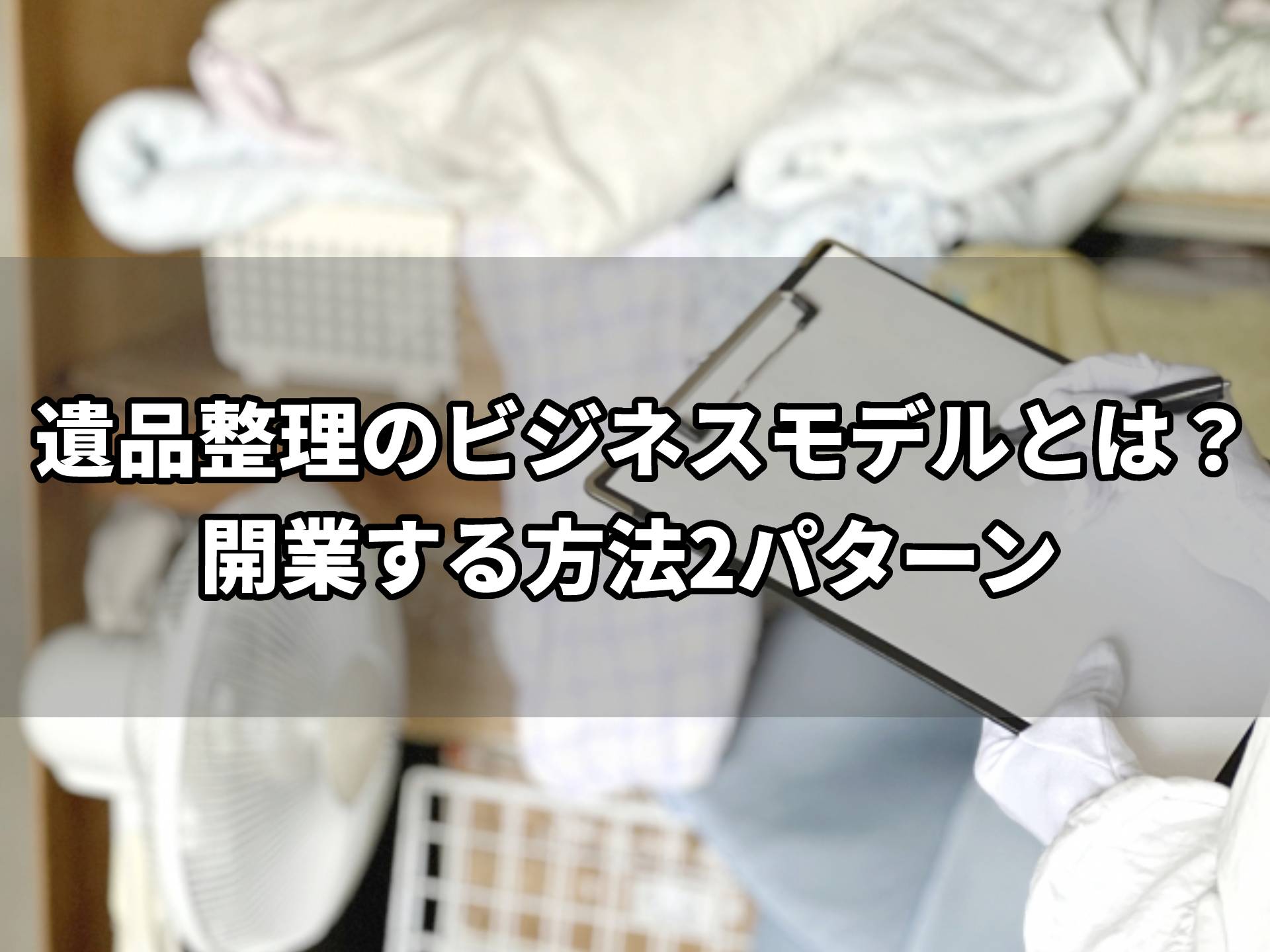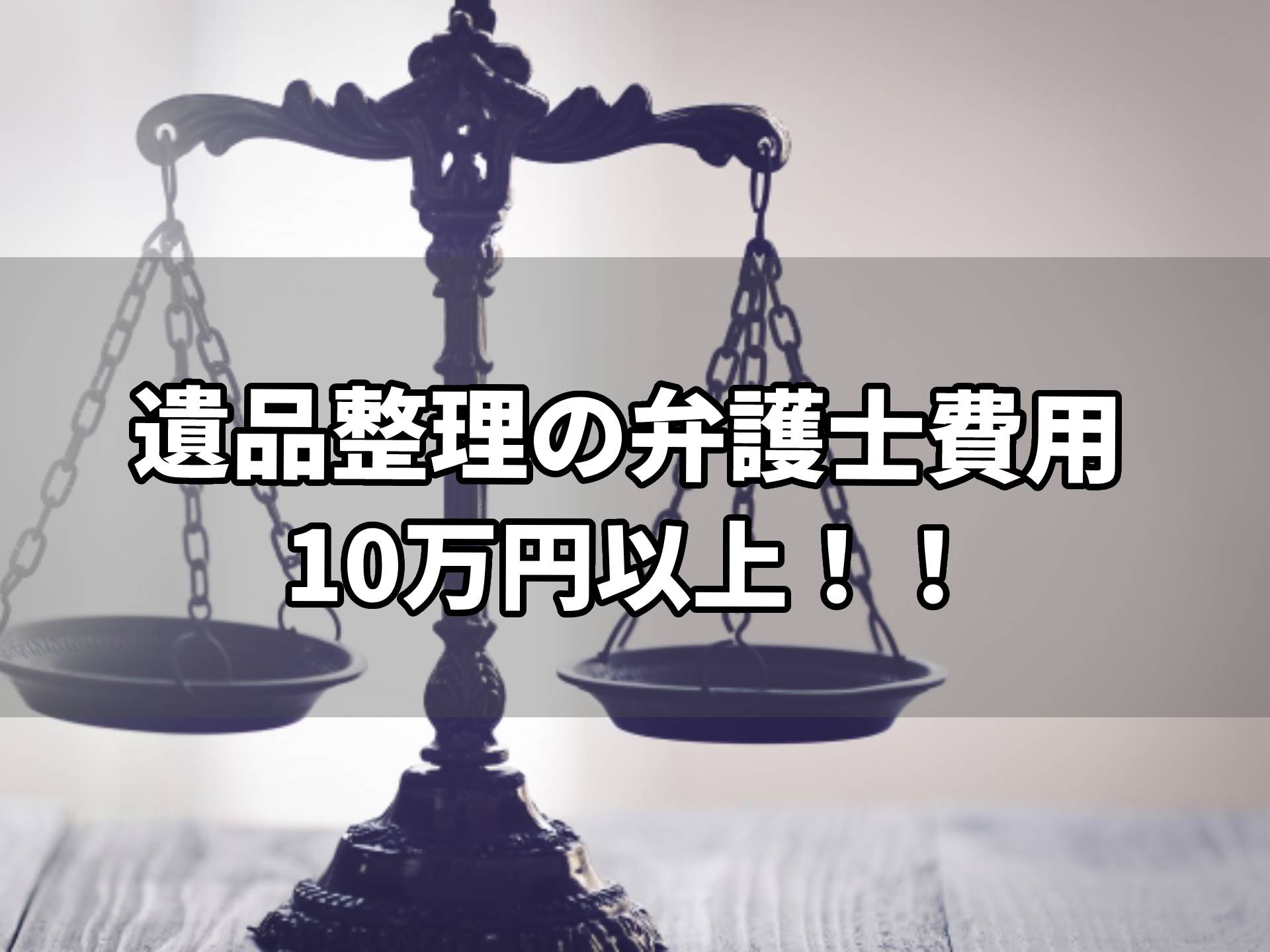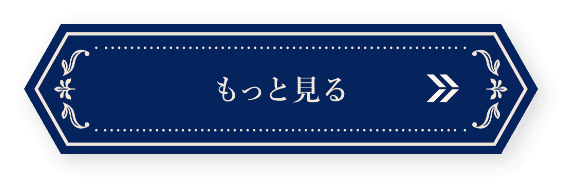遺品整理士の資格は3.5万で最低2ヵ月必要|資格を持つメリット
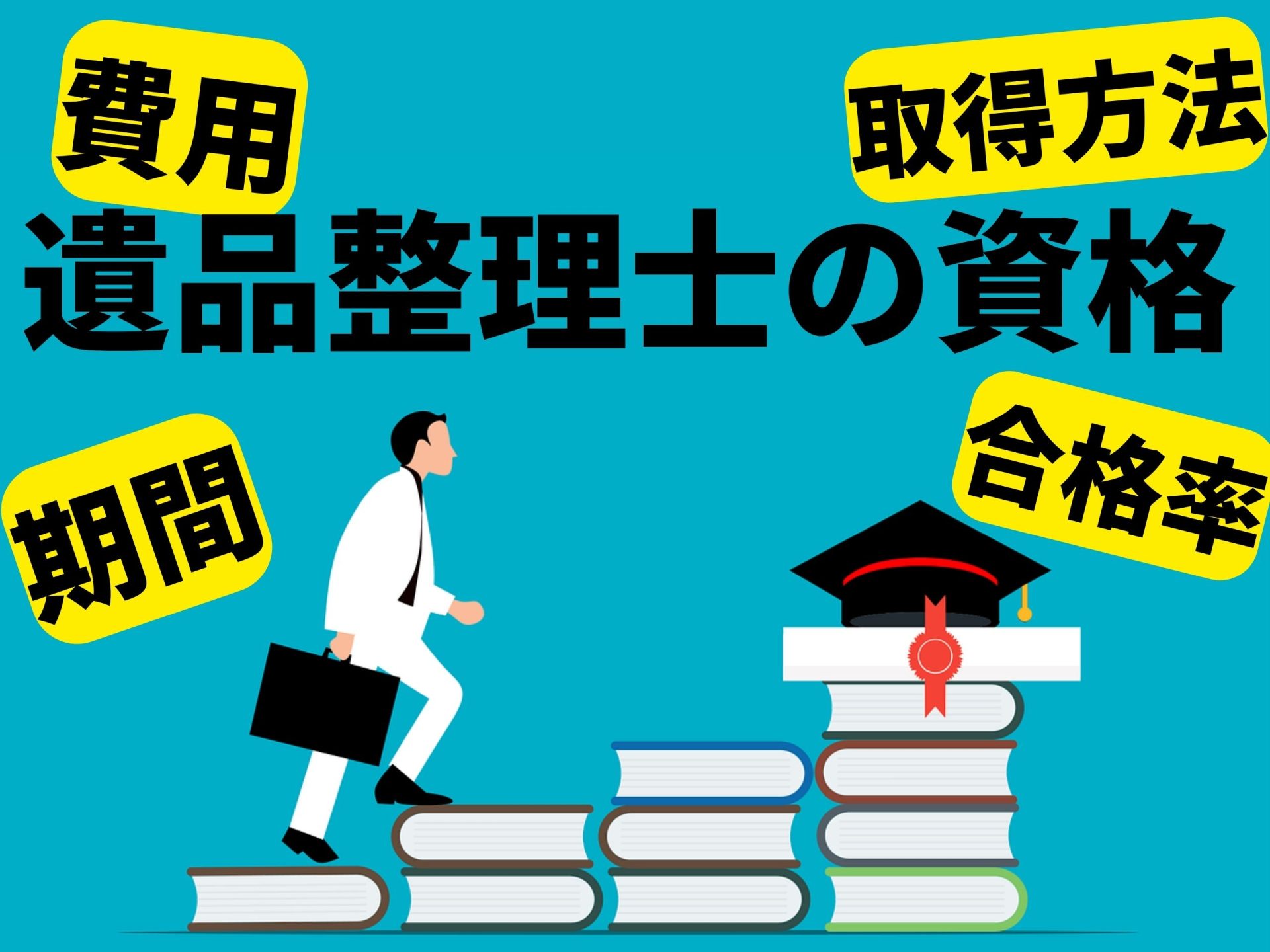
遺品整理士の資格ってどうやってとるんだろう。
「遺品整理士認定協会」が発行している資格で、国家資格ではありません。
遺品整理士は、故人が遺した遺品を大切に扱い、遺族の方にとって大切なものと不要なものに分ける仕事です。
「遺品を処理する」のではなく「遺品を供養する」気持ちで、遺品と向き合います。
少子高齢化が進む日本では、これから需要のある仕事として注目されているのです。
この記事では、遺品整理士の資格の取り方や、遺品整理士の資格をとるメリットをご紹介します。
- 遺品整理士の資格の取り方や詳細
- 遺品整理士の資格を持つメリット
- 遺品整理士の主な仕事内容
後半では、遺品整理士の主な仕事内容に焦点をあてていきます。
あなたに向いている職業なのか、この記事を読んで判断してみてくださいね。
それでは、是非最後までご覧ください。
1:遺品整理士の資格の取り方や資格の詳細を徹底解説

遺品整理士の資格は「遺品整理士認定協会」が発行しています。
遺品整理士認定協会に申し込みをすることで、資格をとることができるのです。
しかし、遺品整理士は民間資格なので、法的効力はありません。
遺品整理士の資格の取り方をはじめ、費用や期間、合格率などを解説していきましょう。
- 資格の取り方
- 資格取得にかかる費用
- 資格取得にかかる期間
- 遺品整理士の資格合格率
それでは、気になる遺品整理士の資格に関して、根掘り葉掘り解説をしていきます。
①:資格の取り方
遺品整理士の資格は「遺品整理士認定協会」に申し込みをすることから始まります。
電話もしくはホームページ上から、申し込みをするのです。
資格取得に年齢制限はないので、誰でも受講をすることができます。
申し込みが完了すると、教材・資料集・問題集・DVDが届くので、勉強をし、レポートを提出することで、資格をとることができるのです。
教本の内容は「遺品整理とは何か」「法規制との関わり」「孤立死問題」など、遺品整理に関係することを学びます。
②:資格取得にかかる費用
資格取得にかかる費用は、35,000円です。
そのうち、10,000円は遺品整理士認定協会の会費となります。
会員は、2年間の有効期限があるので、2年に1度10,000円を会費として支払う必要があるので注意をしましょう。
③:資格取得にかかる期間
資格取得にかかる期間は、最短で2ヶ月です。
問題集に沿って、課題レポートを提出をします。
しかし、無料で受講期間の延長ができるので、2ヵ月でレポートを提出する必要はありません。
④:遺品整理士の資格合格率
遺品整理士の合格率は、65%と言われています。
3人に2人は合格するので、超難関の資格ではありません。
しかし、テストではなくレポートを提出することで合否判定が出るということを認識しておきましょう。
2:遺品整理士の資格を持つ2つのメリット

遺品整理業者で働くのであれば、遺品整理士の資格は取得しておきたい資格です。
遺品整理業界で働かないのであれば、取得する必要はないでしょう。
それでは、遺品整理士の資格を持つメリットを解説します。
- メリット①:仕事が依頼されやすい
- メリット②:依頼者から感謝される
これから需要のある仕事として注目されている「遺品整理士」なので、資格を持っていれば仕事の依頼も受けやすくなります。
メリット①:仕事が依頼されやすい
遺品整理士の資格を持っていると、仕事が依頼されやすくなります。
まず、資格を持っていれば、遺品整理業者の職場に受かりやすくなるでしょう。
そして、依頼者が遺品整理士の資格を持っているスタッフが在籍している遺品整理業者か、在籍していない遺品整理業者の2択で選ぶとしたら、前者を選ぶことは明らかですよね。
これから需要が更に高まる職業の分野なので、資格を持っていて困ることはありません。
メリット②:依頼者から感謝される
遺品整理士の資格を取る際、受講者は遺品整理の仕組みだけを勉強する訳ではありません。
遺品との向き合い方に関しても、学習をするのです。
遺品を整理・処分するのではなく、遺品を供養する気持ちで遺品と向き合います。
また、遺族の方たちへの接し方なども学び、遺族の方たちが気持ちよく遺品整理できるように手助けをするのです。
遺族の方にとって、遺品は故人が最後に残した貴重なものなので、丁寧に扱うことを学ぶことで、感謝をされます。
3:確認しておこう!遺品整理士の主な5つの仕事内容

先ほどもお伝えしたように、遺品整理士の仕事は遺品整理だけではありません。
その他にも、あらゆる仕事をしています。
遺品整理士の主な5つの仕事内容をご紹介します。
- 仕事①: 遺品整理
- 仕事②:遺品の捜索
- 仕事③:遺品の供養
- 仕事④:清掃
- 仕事⑤:事故現場
遺品整理士の仕事は「きつい」仕事とも言われています。
その理由は、遺品整理をする現場が様々な状況である可能性があるからです。
それでは、5つの仕事内容をより詳しく解説していきます。
仕事①: 遺品整理
まずは、なんといっても遺品整理です。
遺品を「必要なもの」と「不要なもの」に分けていきます。
遺品整理の現場には遺族が同席しない場合もあるので、遺品整理は重要な仕事です。
故人が生前大切にしていたものや、貴重品類、重要な書類などは必要なものとして保管をします。
遺品整理士が必要な「大切なもの」として、保管しておくものは以下のようなものです。
必要なもの
- 遺言書・エンディングノート
- 現金
- 通帳・キャッシュカード
- 印鑑
- 権利書や契約書など重要書類
- 手紙や写真
- 身分証明書
- 有価証券
仕事②:遺品の捜索
遺品の捜索を、遺族の方から依頼する場合があります。
一番多いケースは、故人が認知症を患っていて、必要な書類や通帳が見つからないケースです。
遺品整理士は、経験や知識を活かして見つからないような場所にある遺品を捜索する場合があります。
現場によっては、ゴミ屋敷のように不用品が散乱している場所から貴重品を探さなければならないこともあるでしょう。
仕事③:遺品の供養
遺族の方から、遺品を処分する前に供養を依頼されることもあります。
寺院に依頼する場合もあれば、遺品を一度預かって合同供養をすることもあるのです。
仕事④:清掃
遺品整理が終われば、簡単な清掃をします。
賃貸などであれば退去日が決まっているので、清掃まで依頼されるケースも多いです。
現場がゴミ屋敷であれば、不用品の処分から始まり、隅から隅まで掃除をします。
ゴミ屋敷の場合は、虫が湧いていたり、悪臭がしたりと、特殊な薬品を用いて清掃をしなければなりません。
仕事⑤:事故現場
事故現場とは、孤独死や自殺現場で死後遺体発見まで時間がかかった現場のことです。
発見まで時間がかかった遺体からは体液が出て、ウジ虫などの害虫が湧いている場合があります。
感染症などの恐れもあるため、現場は非常に危険です。
素人が事故現場の遺品整理・掃除をすることは不可能なので、遺品整理業者に依頼されます。
「きつい」「くさい」「危険」の頭文字をとった3Kの仕事と考えられ、遺品整理士は「キツイ仕事」と認識されることも少なくはありません。
まとめ
遺品整理士の資格を取る手順や費用などを解説しました。
資格取得には3.5万円必要で、約2ヶ月間かかります。
これから需要が高まり続けていく職業だと考えられるので、遺品整理業界で働きたい方は資格を取得するようにしましょう。
遺品整理士は、人に感謝されるのが好きな人に向いてる職業です。
どんな現場であっても冷静に対応できるような、判断力も欠かせません。
遺品整理業界での就職や、会社の立ち上げをお考えでしたら、遺品整理士の資格は取得しましょう。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。