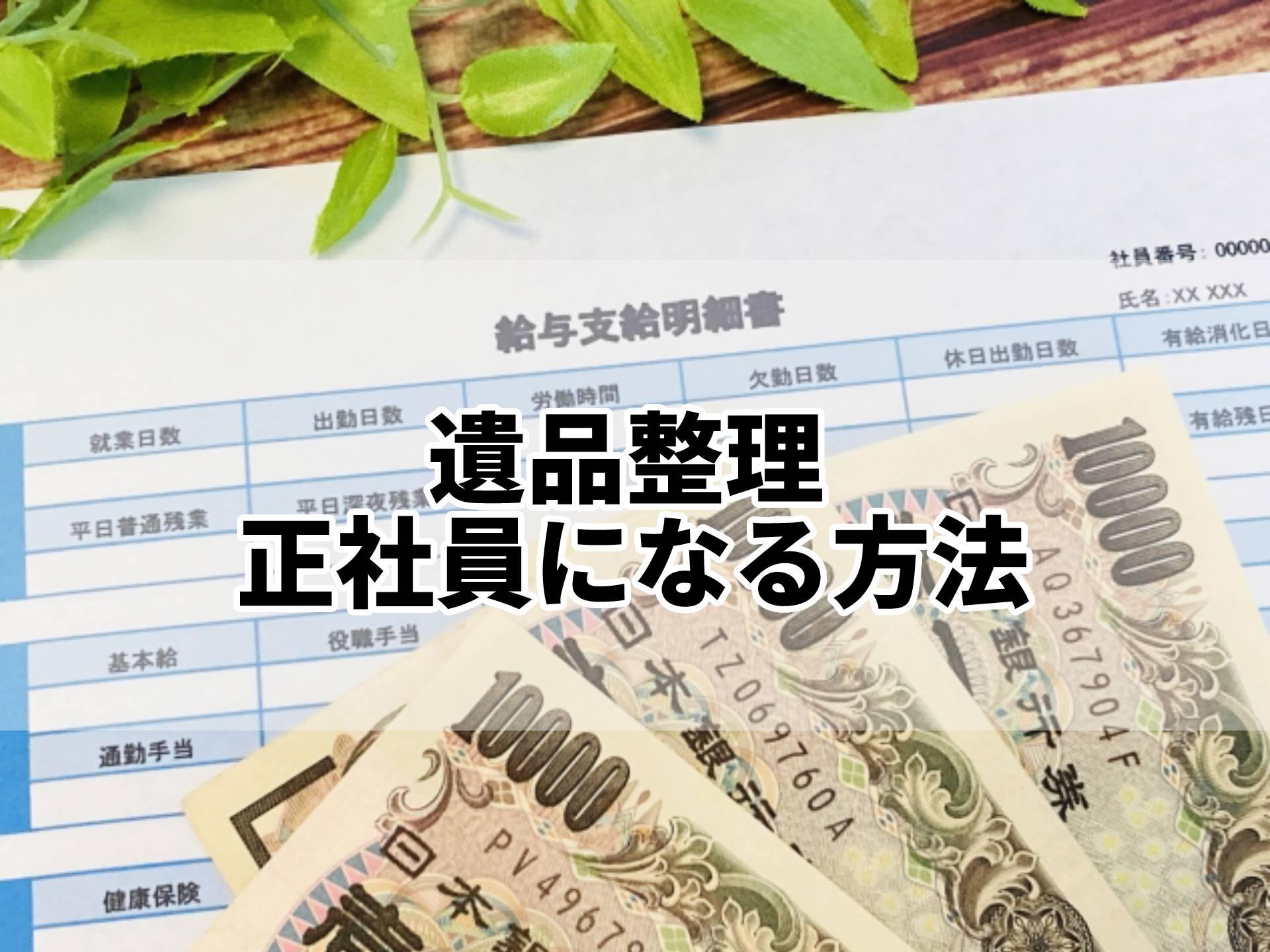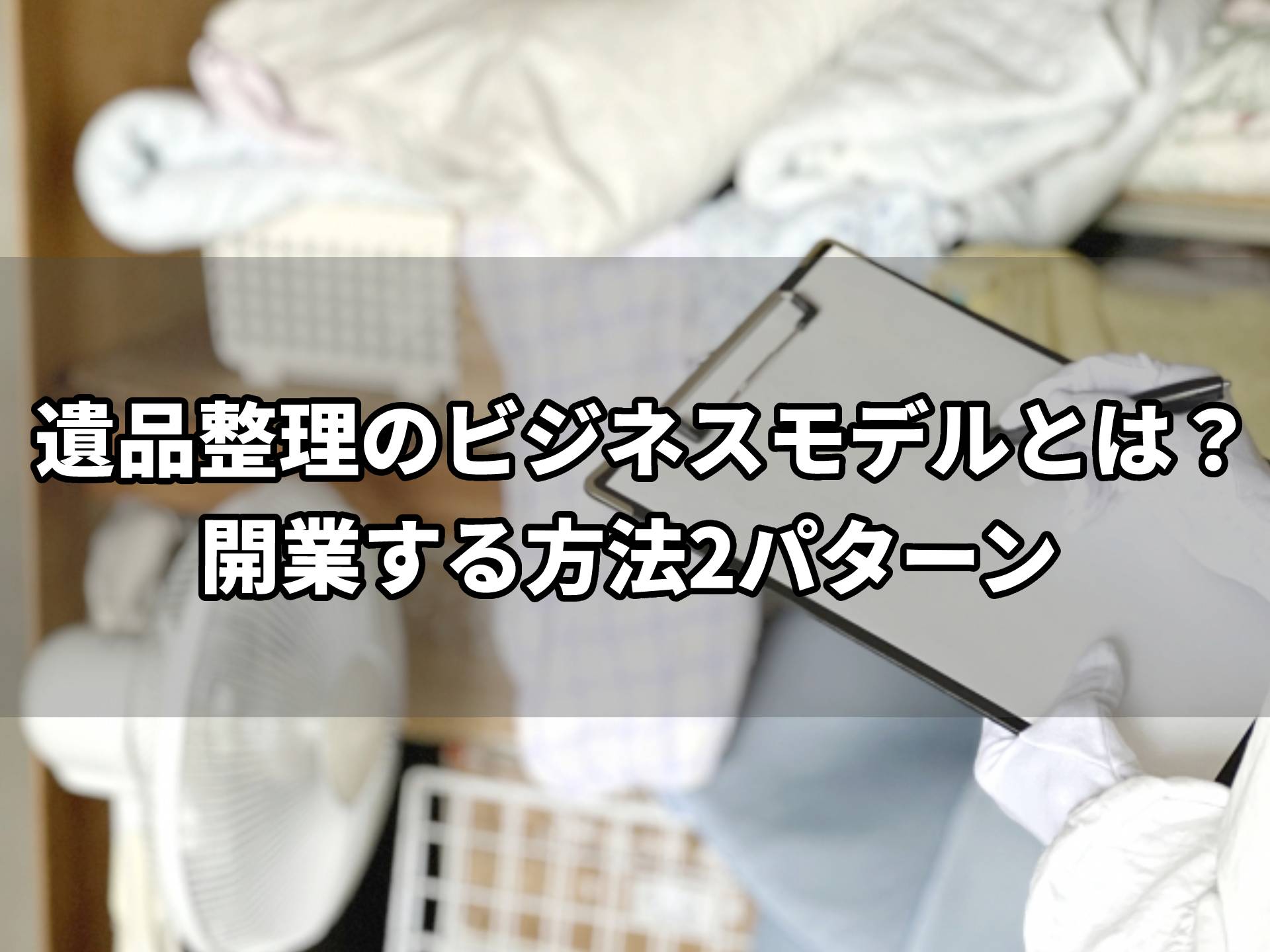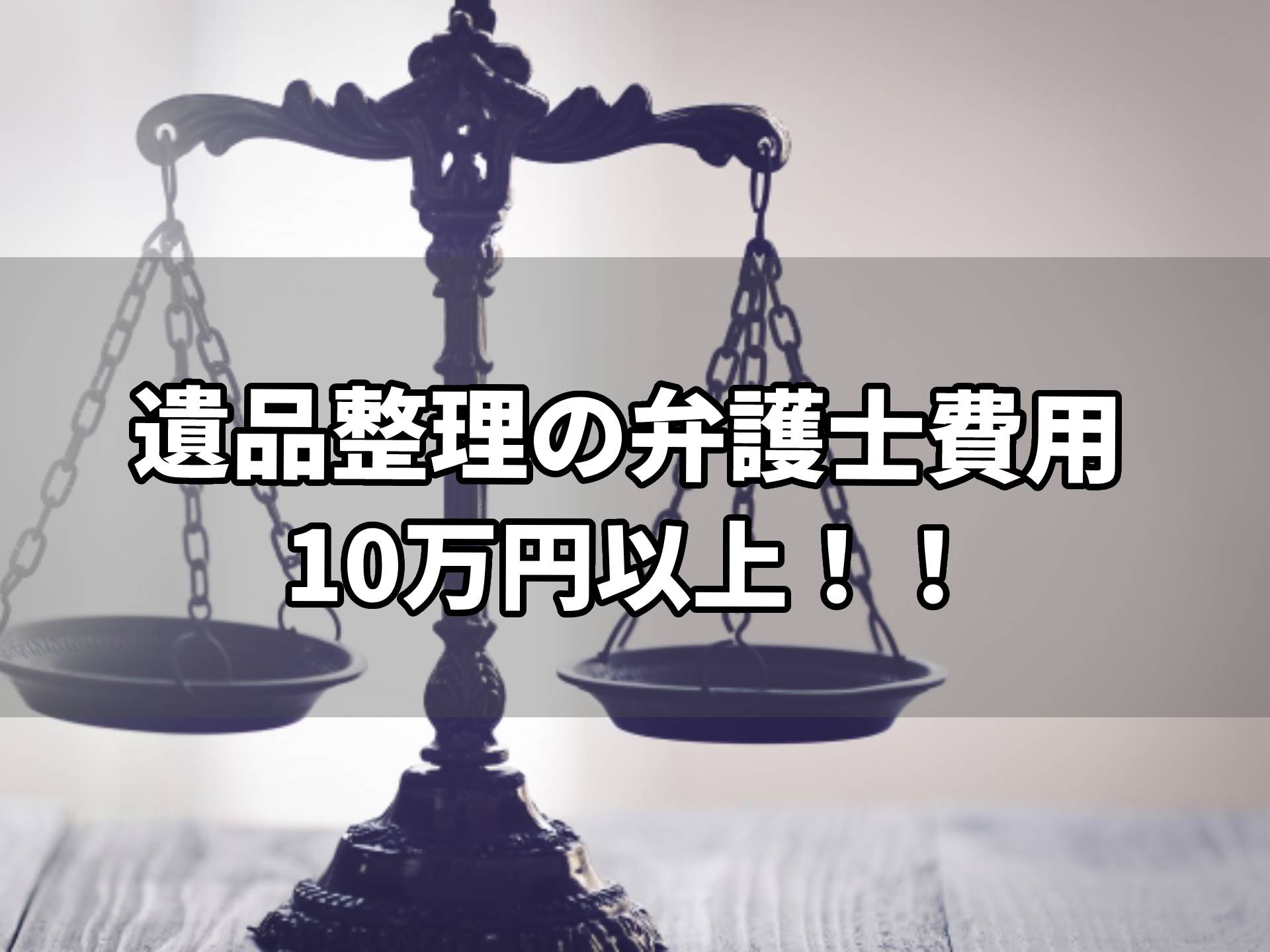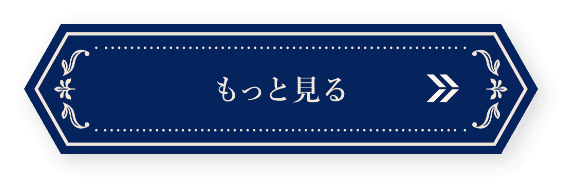遺品整理は誰がやるもの?遺品整理業者を利用すべき状況と注意点

遺品整理って誰がやるものなの?遺品整理業者の存在は知ってるけど信用できる?
遺品整理は本来、故人の遺族が行うものでした。しかし、近年では少子高齢化が進んでいたり核家族が増えていたりする影響を受け、遺品整理業が急速に発達しているのが事実です。どちらも正しい遺品整理の方法なため、どちらが自分に合っているかを判断するとよいでしょう。
今回は、以下の内容でお送りします。
- 遺品整理は誰がやるか
- 遺品の相続について
- 遺品整理の流れ
- 遺品整理の注意点
- 遺品整理業者の料金相場
- 遺品の買取はとらのこ
この記事を読めば、遺品整理を誰が行うか判断することができるでしょう。また、それぞれ誰が行うかによって変わる遺品整理の方法や注意点にも触れていきます。それでは最後までご覧ください。
1. 遺品整理は誰がやる?2つの方法

もともと遺品整理は、故人の遺族が行うことが一般的でした。しかし、日本の社会高齢化や核家族が増えた影響により、遺品整理業者の需要が高くなっているのが現実です。自分たちで遺品整理を行う場合と、遺品整理業者に依頼する場合のメリット・デメリットや、それぞれの注意点などを説明します。
1-1. 自分たちで行う
遺品整理は、精神的にも体力的にも負担が大きい作業となります。費用は抑えられますが、ゴミの廃棄に必要なトラックを借りたり、処分費用などを自らで手配する必要があったりと手間がかかります。しかし、故人との思い出を振り返りながら作業を進めることができるなど、ゆっくりと自分たちの手で整理することができます。
1-2. 業者に依頼する
故人が遠方に住んでいたり、体が不自由だったりと自力で遺品整理を行えない場合は、業者に依頼をしましょう。プロが遺品整理を行うことによって、時間を節約できたり、遺品を見つけ出してくれたりします。また、分別後のゴミの廃棄などもまとめて行ってくれるので、とても便利です。ただし、それなりのコストがかかることを覚えておきましょう。だいたい1Rの部屋で3万円から、一軒家だと20~70万円ほどの費用がかかります。また、最近では悪徳な業者も増えており、トラブルも多く見られています。
2. 法律から見る遺品の相続について

故人の持っていた権利と義務の全てを承継する相続人が基本的に遺品整理の責任をもちます。また、相続人は故人の相続財産を受け取ることもできますが、放棄することもできます。プラスの遺産もマイナスの遺産も手放すということです。その場合は遺品整理も行うことができなくなります。相続放棄は、マイナス資産を受け継がないための手続きですが、一方で形見分けの品でさえ容易に持っていくことはできないなどの制約を受けることになります。
3. これで安心!遺品整理の流れ

簡単に捨てることができなかったり、全く捨てることができないものもなかにはあります。急いで整理する必要があるからといって、全部廃棄してしまっては手遅れになることもあるでしょう。そこで代表的な遺品整理の方法を4つのステップで見ていきます。状況によって正しい遺品整理の手順や方法は異なりますが、あくまでひとつの代表的な流れです。ぜひ参考にしつつ、自分に合った流れを見つけてみてください。
- スケジュールを決める
- 分類する
- 分類したものを処分する
- 残した遺品の分配をする
3-1. スケジュールを決める
まずはスケジュールを立てましょう。いつまでに遺品整理を終わらせる必要があるのか、いつ作業ができるのかを考えるとスムーズに遺品整理を行うことができます。可能であれば、他の親族と話し合って作業を分担したり、遺品整理業者を利用する場合は手配をしたりと色々工夫ができます。しっかりと予定を立てるところから始めることがおすすめです。
3-2. 分類する
遺品は大きく分けて「残すもの」と「捨てるもの」の2つに分類できます。故人が生前に大切にしていた品や思い出の品などの形見になるもの、大事な書類や貴重品を残しておくことが何よりも重要です。また、貴金属や美術品など資産価値のある貴重品なども相続品として形見分けの対象にもなるため、慎重に分類する必要があります。
書類や貴重品リスト
通帳
クレジットカード、キャッシュカード
金
印鑑
身分証明書(パスポートなど)
健康保険証
契約書類
この他にも残しておいたほうがいいものは、リサイクルとして中古販売できる品です。再利用できるものは、買取業者や不用品回収業者に依頼したり、フリマアプリなどを利用したりして買い取ってもらいましょう。
リサイクル品リスト
大型の家電
小型家電
家具
衣服
金属類
3-3.捨てるものを処分する
残すものが判断できたら、それ以外は廃棄します。燃えるゴミや燃えないゴミは、自治体で決められた集積所へ持ち込んで処分します。自治体によって廃棄方法が異なることがあるため、廃棄する地域の自治体に確認しておきましょう。捨てるものの量によっては、買取業者や不用品回収業者に依頼することもひとつの手です。状況に応じて判断してください。
3-4. 残した遺品の分配をする
資産価値のある相続品は、平等に分配します。高価な宝石や芸術品、美術品などは、買取を行ったうえで分配ができます。また、価値の有無に関わらず、故人の想い出がある遺品は形見分けします。
形見品リスト
身に着けていたアクセサリー
衣類
趣味のコレクション
時計
書籍
これらは親族で分配することが一般的です。高価な遺品は、贈与税の対象になる場合があります。形見分けの相手の負担にならない遺品を選ぶようにしましょう。
4. 遺品整理業者の料金相場
業者を利用して遺品整理を行うにはいくらかかるのか調べてみました。間取りや遺品の量、作業時間によっても異なるため一概には言えません。間取りごとの価格を参考にして大体の相場の目安にしましょう。
| 間取り | 費用相場 |
| 1R | 30,000~ |
| 1DK | 40,000~100,000円 |
| 2DK | 80,000~150,000円 |
| 2LDK | 120,000~200,000円 |
| 3DK | 190,000~220,000円 |
| 3LDK | 220,000~250,000円 |
| 4DK | 280,000~300,000円 |
| 4LDK | 300,000~円 |
基本的に作業する部屋の広さや部屋数に比例して料金が高くなります。部屋が広くなればなるほど、作業時間が増えて人員も多く必要になるため、料金は高額になります。
5. 遺品整理の2つの注意点

自分に合った遺品整理方法の目処がついたところで、実際に作業にとりかかる前に、これだけは気を付けてほしい注意点を2つご紹介しておきます。失敗してからでは手遅れになることがあります。以下の注意点をふまえて、丁寧な遺品整理を心がけましょう。
- 悪徳な業者には気を付けよう
- 親族と協力して行おう
5-1. 悪徳な業者には気を付けよう
遺品整理業者においても、不用品回収業者においても、なかには許可を得ていない違法業者が多く存在します。遺品の買取などを行う際に必要な「古物商許可」や、不用品を捨てる際に必要な「一般廃棄物収集運搬業許可」などがあります。こういった違法業者を見分けるポイントは3つです。まず料金が安すぎること、訪問しないで見積もりを出すこと、ホームページなどに情報がないことが判断の基準となります。高額の請求を求められたり、遺品を盗まれたりと直接被害に合う可能性を考えて、業者選びをしましょう。
5-2. 親族と協力して行おう
遺品を処分するときには、故人と親しかった相続人以外の親族にも相談しましょう。深い間柄であった友人にも確認することをおすすめします。トラブルとして考えられるのは、遺品整理後に、遺品整理することを知らなかった親族が受け取るはずだった形見をすでに処分してしまったときです。すでに廃棄してしまったあとでは取り戻すこともできず、弁償して済むものでもありません。なるべく親族全員と協力しながら遺品整理は行いましょう。
6. 遺品の買取はとらのこで
自分たちで遺品整理を行った場合、リサイクルできるものを捨てるのはもったいないと思いがちですよね。不用品を廃棄する前におすすめしたいのが、出張買取の利用です。遺品整理後に買取業者が訪問し、価値のつく遺品を買い取ってくれます。
弊社とらのこは、そんな出張買取に力を入れている買取業者です。
「訪問」「査定」「キャンセル」など全てを無料で対応しており、お客様の負担は一切ありません。
不用な家具、家電、スポーツ用品など取扱いジャンルは豊富で、1点からの買取も承っております。お気軽にご相談ください。
まとめ
いかがでしたか。今回は、一般的な遺品整理を誰がやるかを筆頭に遺品整理の流れについてもご紹介しました。相続放棄した人は遺品整理が行えなくなるといった注意も必要です。
自分たちで行うか、遺品整理業者に依頼をするかそれぞれのシチュエーションに合わせて判断しましょう。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。