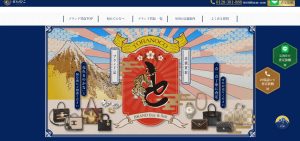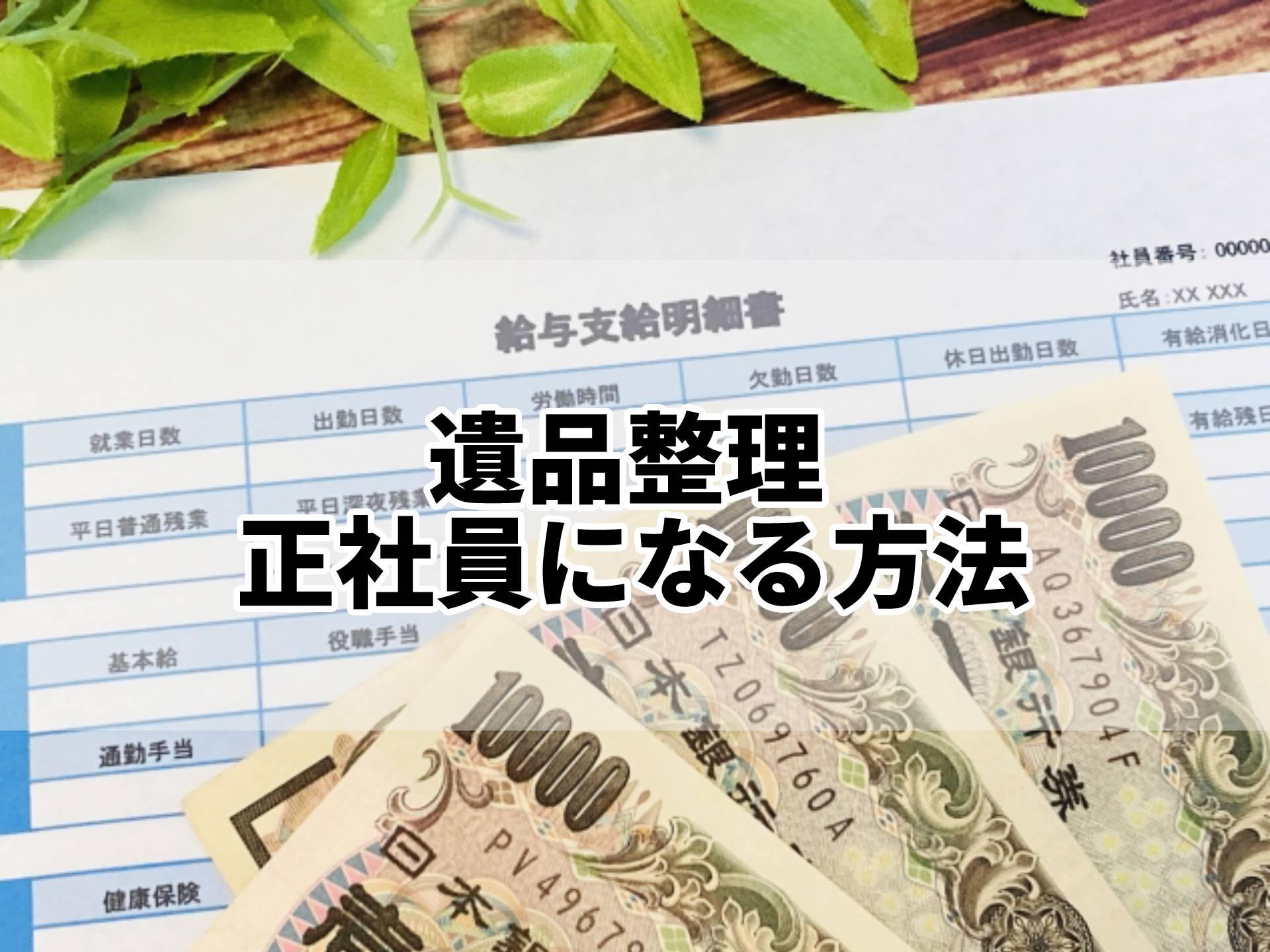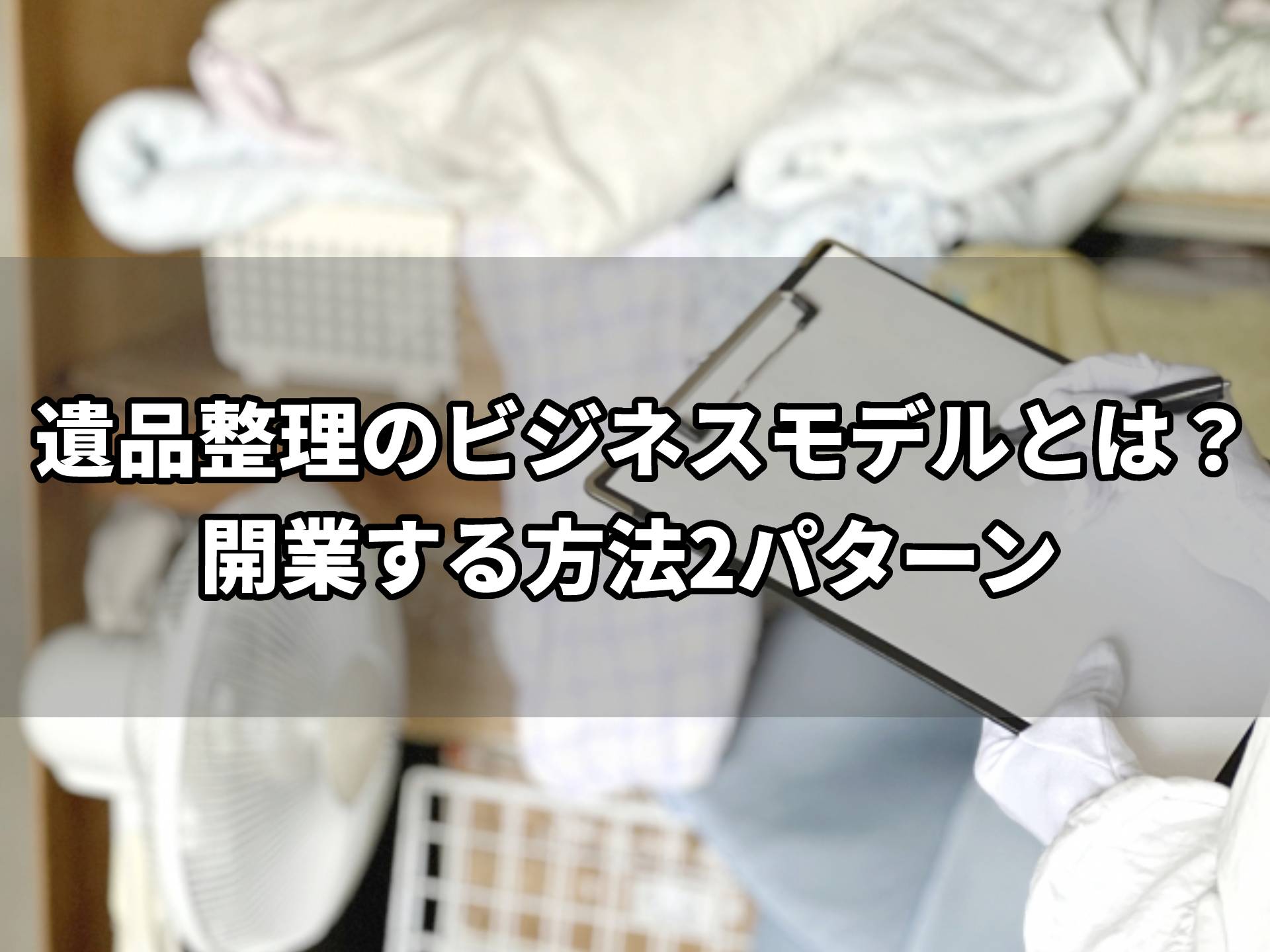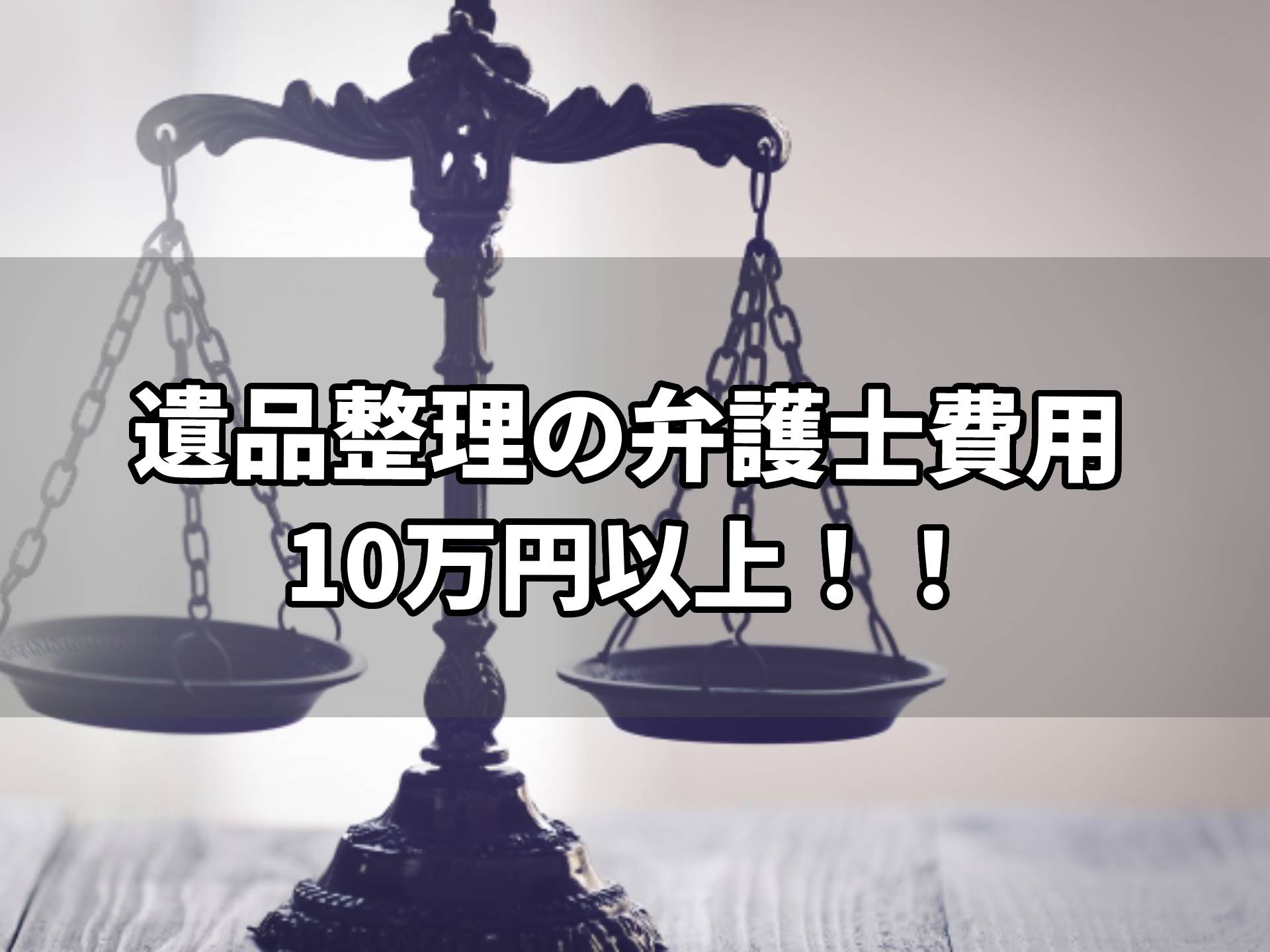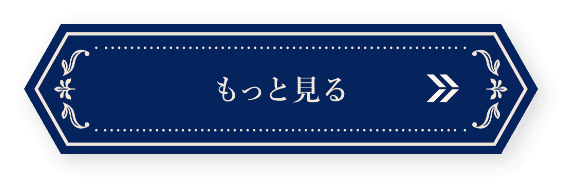遺品整理は家族の負担?生前整理を行う方法とタイミングを解説
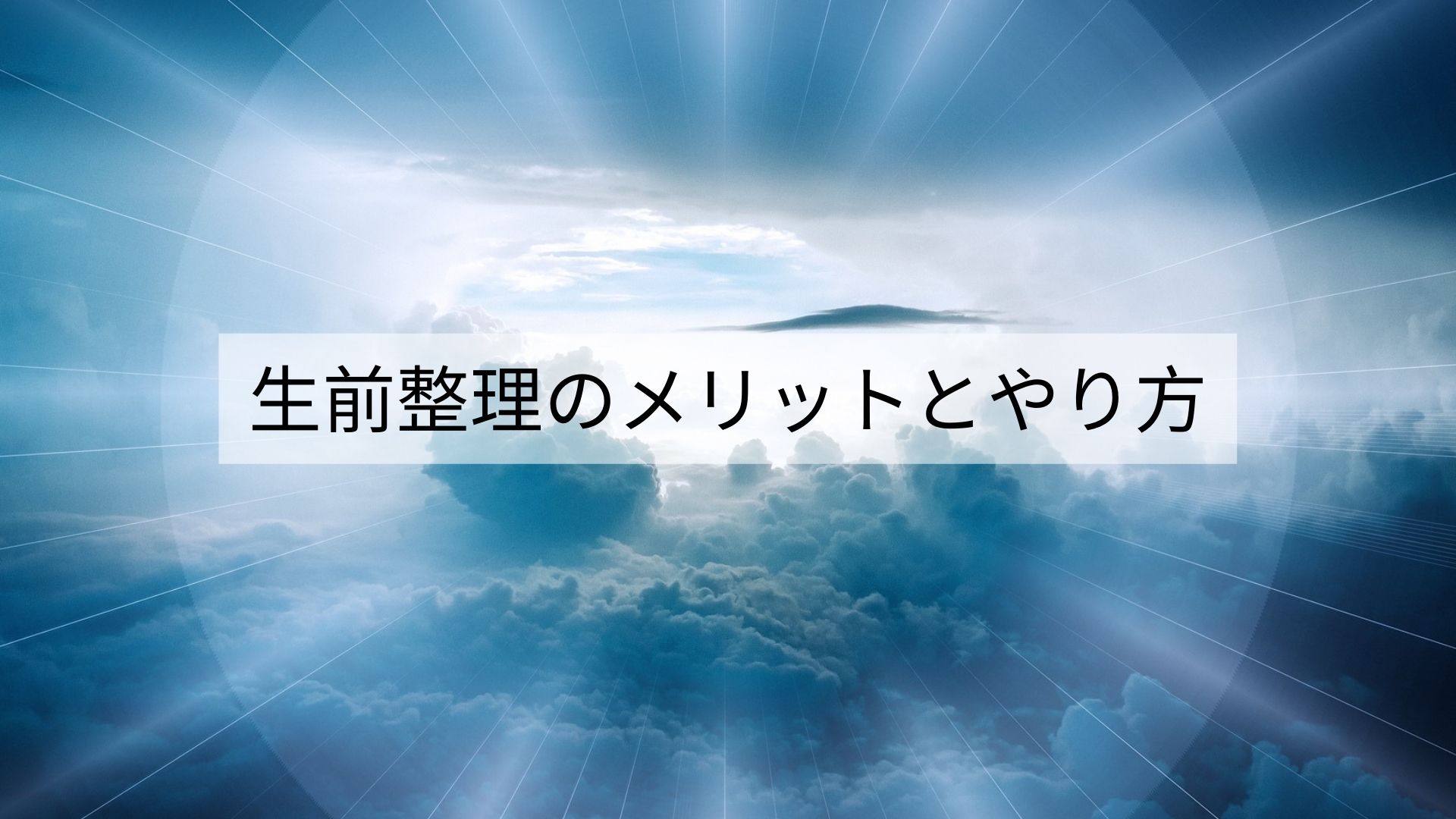
家族に迷惑をかけたくないから、生前整理を考えているけれど…。
身体が自由に動くうちに、所有物の生前整理を行いたい方も多いですよね。「これだけは捨てないで!」という品もなかにはあると思います。家族の負担を減らすためにも、今の自分の生活を豊かにするためにも生前整理はおすすめです。
今回は、以下の内容でお送りします。
- 遺品整理と生前整理のちがい
- 生前整理を行うメリット
- 生前整理の流れ
- 生前整理をはじめるタイミング
- 不用品の買取は【とらのこ】
この記事を読めば、生前整理を考えている方でも、明日からすぐにはじめられます。それではさっそく見ていきましょう。
1. 遺品整理と生前整理のちがい

遺品整理は、故人の死後に遺族が行う持ち物の整理のことを言います。それに対して生前整理は、死を見添えた本人が生きているうちに行う持ち物の整理のことです。
2. 生前整理を行う4つのメリット

なにごとも早いうちに済ませておくのが吉と言われますが、遺品整理を生前に予約することによってどんなメリットがあるのでしょうか。ここでは、考えられる4つのメリットを紹介します。
- 家族や親戚の負担を減らす
- 家族の相続トラブルを防げる
- 自分の生活環境を整えられる
- 余生を謳歌できる
2-1. 家族や親戚の負担を減らす
遺品整理は、一般的に故人の家族や親族の方が行います。しかし、故人の死亡後は葬式や届け出の準備などで忙しくなるでしょう。どうしても負担をかけたくないという方には、自らで整理しておくのがおすすめです。遺族にとって金銭的・時間的・精神的な負担を減らします。
2-2. 家族の相続トラブルを防げる
生前に自分の財産の分配を決めることができるため、家族の相続トラブルを防げます。
なにも準備しないまま遺族へ財産を引き継ぐと、相続トラブルが起こる可能性が考えられるでしょう。揉めるほど財産がないと考えていても、預貯金や貴金属・アンティークといった形見の品で争う遺族も出てきます。
遺産相続で家族が争うことのないように、遺産を誰に残すのか明確に示しておきましょう。
2-3. 自分の生活環境を整えられる
所持品を整理することによって、自らの生活環境を整えられます。
年齢をある程度重ねると思い入れのある物が増えていき、使用していないものもたまっていくでしょう。生前整理をすることによって、残りの人生で本当に必要なものが見えてきます。
2-4. 余生を謳歌できる
だれでも他人に迷惑をかけることに対して抵抗があると思います。遺品整理業者に生前予約などをしておくと、自分の死後の心配をする必要がなくなるため、心おきなく残りの人生を楽しむことができるでしょう。生きている間に自分の荷物の整理を行うことで、大切な品をしっかり管理できたり、思い出を振り返れたりします。
3. これで安心!生前整理の流れ

生前整理といっても、基本的には所有物の整理整頓がほとんどの作業となります。それに加えて生前整理ならではの、遺言書を残しておくなどの作業が必要です。ここでは、簡潔に生前整理の流れを解説していきます。
- スケジュールを決める
- 分類する
- 捨てるものを処分する
- 遺言書を作成する
3-1. スケジュールを決める
まずはスケジュールを立てましょう。いつまでに生前整理を終わらせる必要があるのか、いつ作業ができるのかを考えるとスムーズに行うことができます。可能であれば、家族と話し合って作業を手伝ってもらったり、遺品整理業者を利用する場合は手配をしたりと色々工夫ができます。しっかりと予定を立てるところから始めることがおすすめです。
3-2. 分類する
大きく分けて「残すもの」と「捨てるもの」の2つに分類できます。これまで大切にしていた品や思い出の品などの形見になるもの、大事な書類や貴重品を残しておくことが何よりも重要です。また、貴金属や美術品など資産価値のある貴重品なども相続品として形見分けの対象にもなるため、慎重に分類する必要があります。
書類や貴重品リスト
通帳
クレジットカード、キャッシュカード金
印鑑
身分証明書(パスポートなど)
健康保険証
契約書類
この他にも残しておいたほうがいいものは、リサイクルとして中古販売できる品です。再利用できるものは、買取業者や不用品回収業者に依頼したり、フリマアプリなどを利用したりして買い取ってもらいましょう。
リサイクル品リスト
大型の家電
小型家電
家具
衣服
金属類
3-3.捨てるものを処分する
残すものが判断できたら、それ以外は廃棄します。燃えるゴミや燃えないゴミは、自治体で決められた集積所へ持ち込んで処分します。自治体によって廃棄方法が異なることがあるため、廃棄する地域の自治体に確認しておきましょう。捨てるものの量によっては、買取業者や不用品回収業者に依頼することもひとつの手です。状況に応じて判断してください。
3-4. 遺言書を作成する
遺言書は法的効力をもつため、遺産相続に関することを書いておきましょう。遺言書を残しておくと、自分の財産を意に沿った形で相続人にわたすことができます。遺言書を残していない場合は、死後に相続人同士で遺産分割協議をする必要があり、そこから相続トラブルに発展する可能性もあるのです。できるだけ遺言書は作成しておきましょう。
4. 生前整理をはじめるタイミング

基本的に生前整理は、今からでもはじめていいとされています。健康体で病気とは縁遠い生活を送っていたとしても、事故などに巻き込まれることも。生前整理を行っておいて損はありません。高齢者の方は、身体が自由に動くうちに作業をはじめることをおすすめします。なかなかまだ生前整理をはじめられない!とお考えの方に、以下の2つのタイミングが訪れたら生前整理をはじめるきっかけだと捉えてみてください。
- 子どもが家を出たとき
- 70歳を迎えたとき
4-1. 子どもが家を出たとき
進学や就職、結婚などにより子供が家を出たタイミングは、生前整理をはじめるきっかけの1つとなります。
子供と一緒に住む環境でなくなった時点で生前整理を行っておけば、あなたの身に何か起こった場合でも、家族は所有物の整理をしやすくなります。
4-2. 70歳を迎えたとき
70歳になったときに生前整理を行うのもいいタイミングといえます。厚生労働省の政府統計資料によると、2016年時点での日本人の平均健康寿命は、男性で72.14歳、女性で74.79歳となっています。健康寿命とは健康上問題なく、自力で生活を送れる期間のことを言います。
生前整理は自力で行うことが大切なので、身動きがとれるうちに行っておくのがおすすめです。
5. 不用品の買取は【とらのこ】
生前整理を行い、捨てるまでにはいかない再利用できる品があれば、出張買取で売ってみましょう。大量の荷物であっても運び出す必要がないので、とても便利です。
とらのこは、全国規模で出張買取を承っております。
さらに「見積もり」「出張」「キャンセル」を全て無料で行っており、手数料は一切かかりません。
双方の都合があえば、即日対応も行っているためスムーズに対応してくれます。
買取対象商品は幅広く「こんなものでも売れるの?」といった遺品にも価値がつく場合があります。ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ
いかがでしたか。生前整理の流れやタイミングについて解説しました。やっておいて損はないので、気が向いたときにぜひ作業をはじめてみましょう。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。