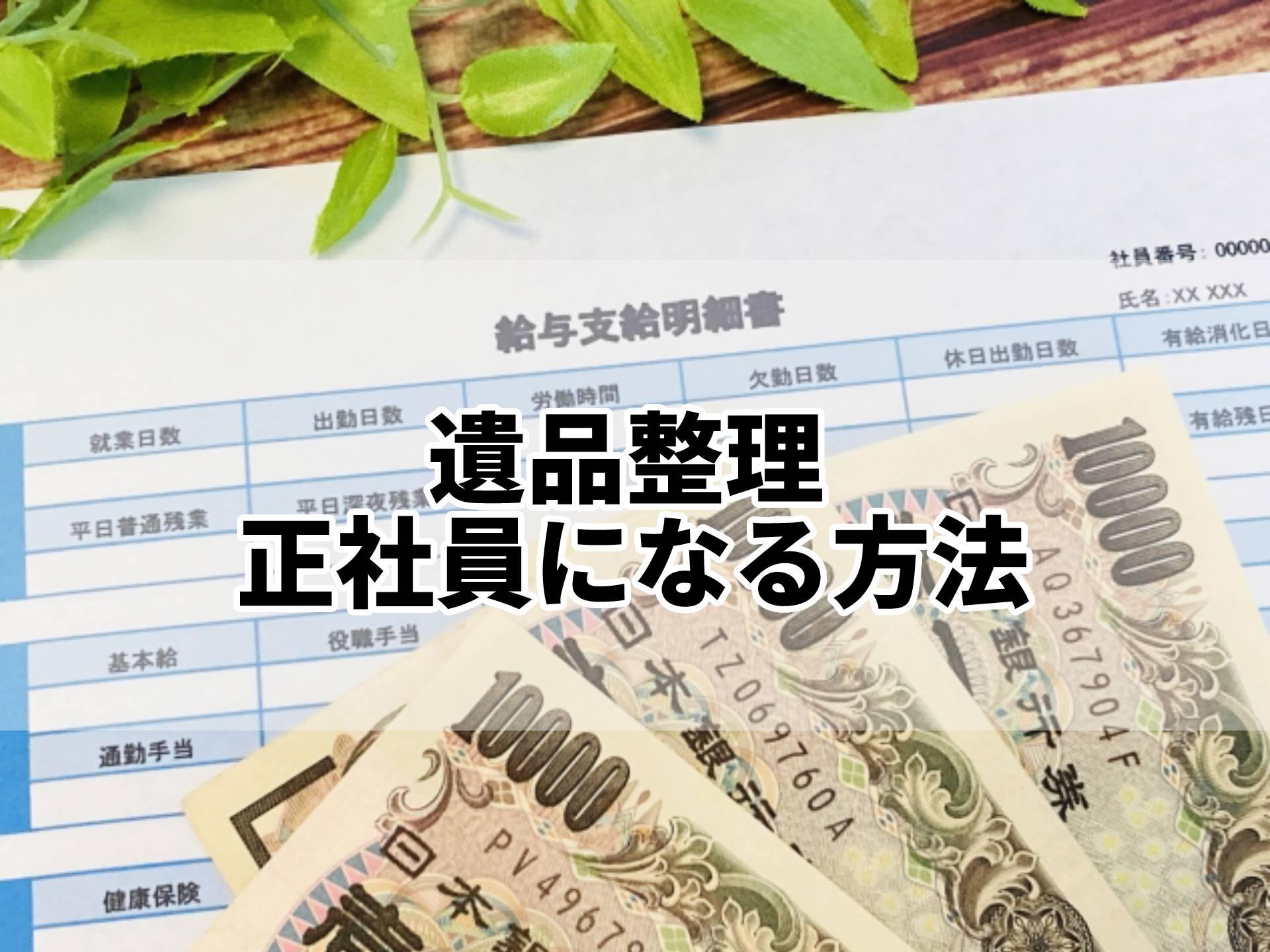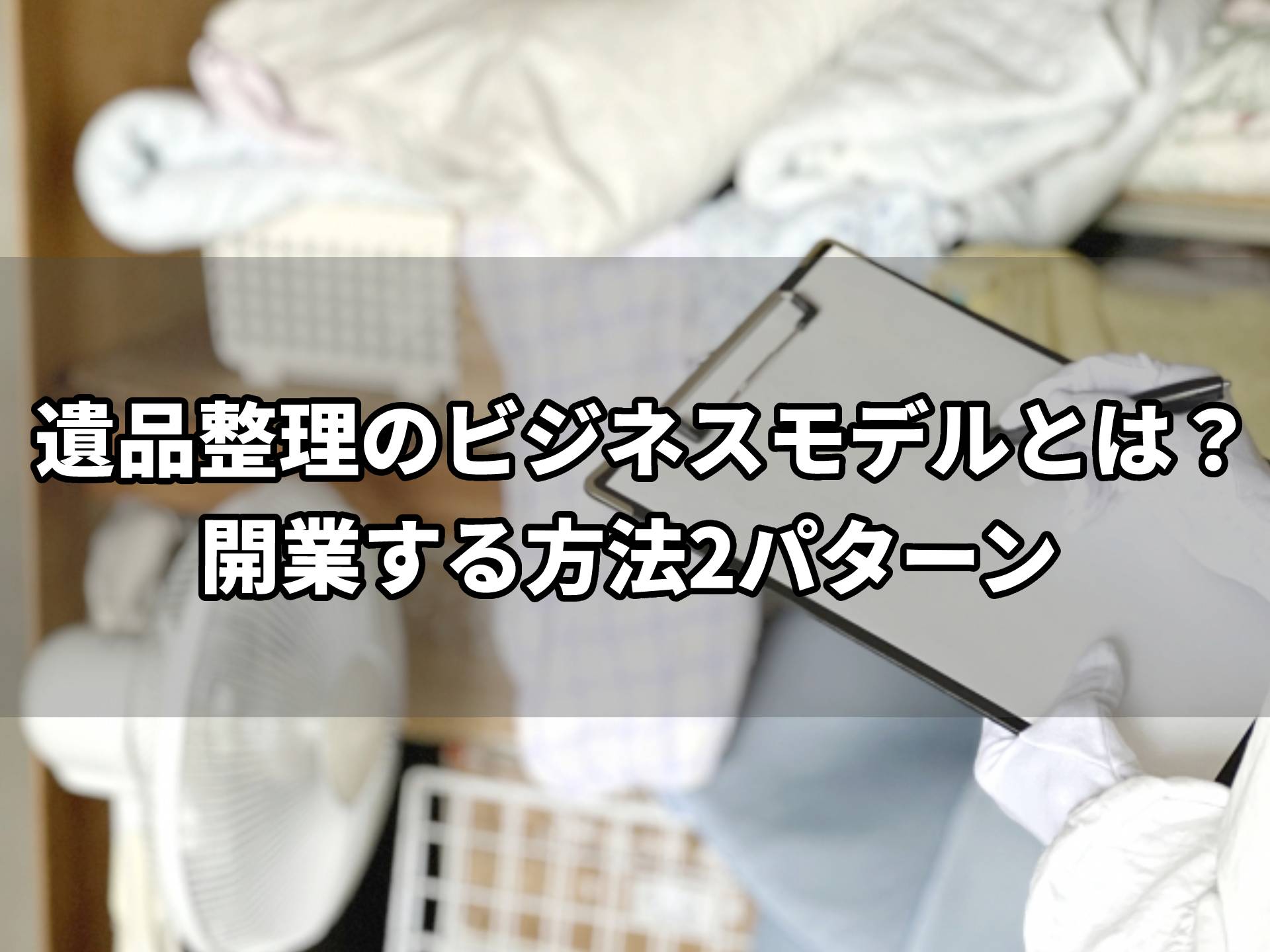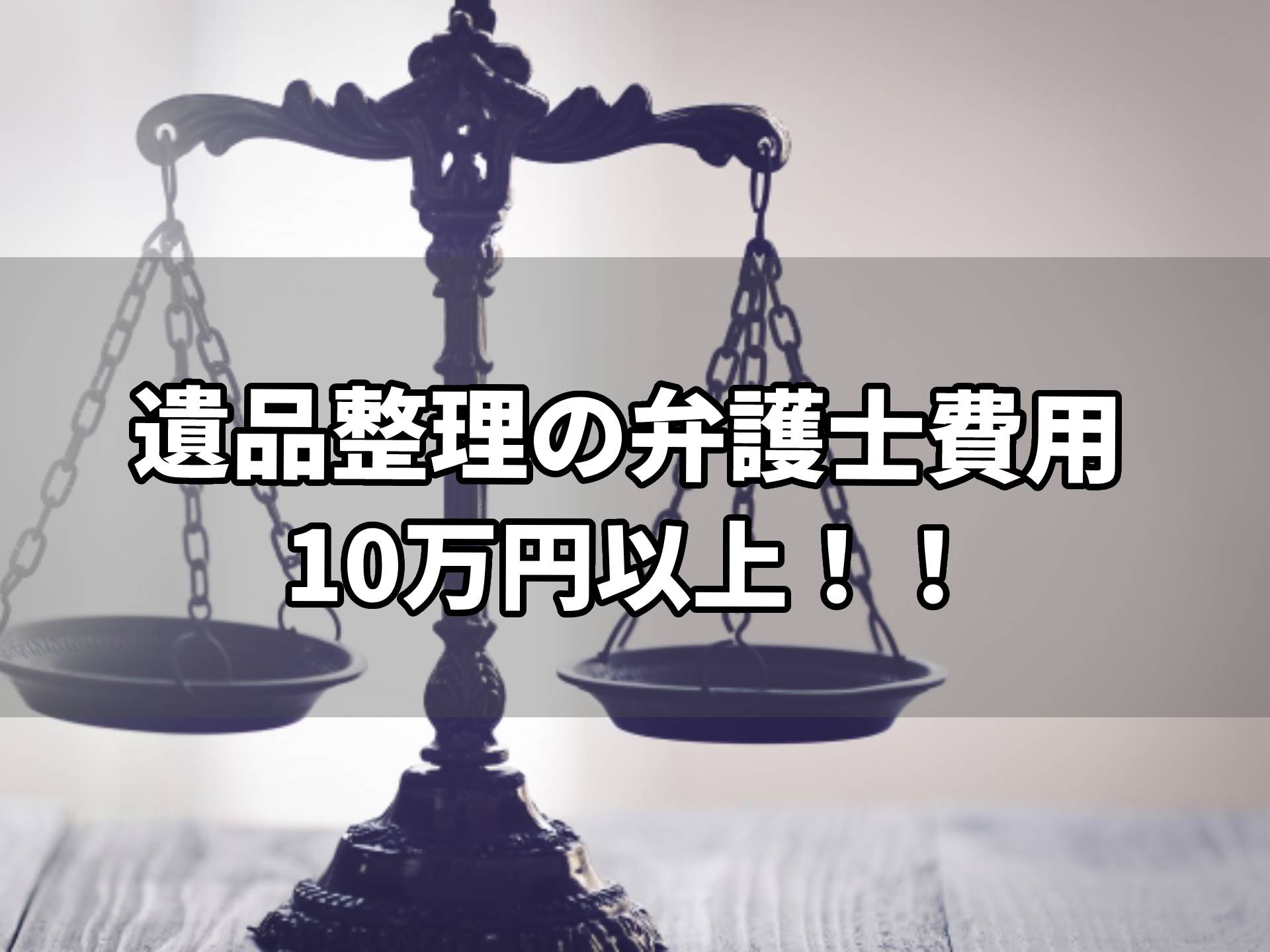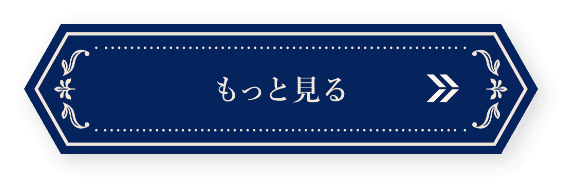遺品整理士の求人募集サイト3選!仕事内容や体験談も紹介

遺品整理の求人募集が気になる…。
新しい仕事を探しているときに見つけた「遺品整理業」は、一体どのような仕事なのか気になりますよね。そんなときは、実際に募集をかけている企業に目を通してみるといいかもしれません。また、遺品整理士の詳しい仕事内容や、体験談などもあわせて紹介していきます。
今回は、以下の内容でお送りします。
- 遺品整理の求人募集を見るサイト
- 遺品整理の求人に応募するときのチェックリスト
- 遺品整理士とは?
- 遺品整理士の体験談
この記事を読めば、遺品整理の求人募集や、実際の仕事内容について理解できます。それではさっそく見ていきましょう。
1. 遺品整理の求人募集を見る3つのサイト
ここ数年で遺品整理の需要が増えたことにより、遺品整理業者の数も増えてきました。そのため、遺品整理士としての仕事を探すことは決してそこまで難しくはないでしょう。ここでは遺品整理業者のなかでも、自分に合った働き場を見つけるための3つの求人サイトを見ていきます。
- Indeed
- 求人ボックス
- タウンワーク
1-1. Indeed
1-2. 求人ボックス
1-3. タウンワーク
2. 遺品整理の求人に応募するときのチェックリスト

仕事の求人に応募するときに必ず確認すべき項目がいくつかあります。実際に働きはじめてから失敗しないために、これから説明する6つの項目をしっかり確認しましょう。
- 起業メッセージ
- 事業内容
- 仕事内容
- 勤務地
- 雇用形態
- 給与
2-1. 企業メッセージ
企業メッセージには、その企業の強みや今後のビジョンが記されています。自分が大切にしている概念がその企業にあてはまるかというのは、これから一緒に働いていくうえで重要になります。また、企業がどのような人を雇いたいのかはここから分かるでしょう。
2-2. 事業内容
事業内容には、企業がどのような事業に取り組んでいるのかが記されています。その企業がどのような事業で利益を得ているのかをしっかり確認しましょう。またここでは、企業が人材を探している理由を知ることができます。「新規事業展開のため」「事業拡大のため」「欠員募集」のためといった理由が考えられるでしょう。これにより、自分が入社したときのポジションをある程度予測することができます。
2-3. 仕事内容
仕事内容には、企業の事業内容が細分化されて記されています。担当する業務や配属先についての情報や、入社後の研修や評価体制などについて書かれていることも。遺品整理といっても、仕分けから遺品の搬出、クリーニングなどさまざまなステップがあります。作業を全て行うのか、部分的に行うのかなど確認しておきましょう。
2-4. 勤務地
勤務地には、本社や面接場所とは別で実際に働く場所がどこなのかが記されています。大きな遺品整理業者であると、全国を規模に事業を展開しているところもあるでしょう。そういった場合は各地域ごとに事業所が分かれているので、自分の希望する地域で募集がかかっているのか確認するべきです。
2-5. 雇用形態
雇用形態には、正社員・契約社員・アルバイト・パート・業務委託といった雇われ方が記されています。遺品整理業には、正社員でもアルバイトでも同数の募集がかけられているため、自分に合った働き方を見つけることが可能です。
2-6. 給与
給与には、応募条件を満たしている場合の基本的な給料が記されています。仕事内容がどれだけラクでも、給与が見合っていなければ時間を無駄にする可能性があるでしょう。遺品整理の仕事が未経験であっても、どのようなタイミングで給与を上げることができるのかなど、確認しておくことが大切です。
3. 遺品整理士とは?仕事内容から年収まで

社会の高齢化と核家族化によって需要が高まっているのが「遺品整理」です。遺族がおこなうのが一般的でしたが、現在ではプロの遺品整理士に任せることも急速に増えてきました。「遺品整理」では、亡くなった人の持ち物を整理し、部屋をきれいに清掃します。遺品のなかには、貴重品などの相続に関するものも多く、細かい部分までしっかりと確認しながらの作業が重要です。
- 仕事内容
- 資格と取得方法
- 年収
3-1. 仕事内容
遺品整理士の主な仕事内容は、故人が使っていた部屋を片付けることです。遺品整理をすることが困難な遺族に代わり、整理業務を行います。代表的な仕事内容はこちらです。
- 必要品と不要品の仕分け
- 不用品の回収と適切な処理
- 家財の搬出
- 整理後の簡易清掃
3-2. 資格と取得方法
遺品整理士になるにあたって、資格の取得は必須ではありません。しかし、所持していれば信頼度がアップします。遺品整理士は、一般社団法人・遺品整理士認定協会の認定資格です。法令に沿った廃棄物処理方法や、遺品の取り扱いや遺品整理に関係する法律について講義を受け、合格した人だけが取得できます。ここでは、資格の取り方を3つのステップに分けて説明します。
・講座を受ける
遺品整理士認定協会へ電話、もしくはWEB上から、遺品整理士養成講座の申し込みをします。受講資格は特になく、誰にでも受講ができます。目安としては約2カ月の間、通信講座を受講するだけです。
申し込み手続きが完了すると、教本、資料集、問題集、DVDが届くので、受講を開始します。受講内容は、遺品に接する際の心構えについて、そして廃棄物を処理するための法律についてなどです。受講期間を延長したい場合は、遺品整理士認定協会へ連絡をしてみましょう。無料で受講期間を延長してくれます。
・課題レポートを提出する
講座の受講を終えたら、問題集に沿って遺品整理士認定協会へ課題レポートを提出します。レポートは郵送、もしくはWEB上で提出ができます。合否を決定づけるレポートです。提出が完了したら、合否通知を待ちます。合否通知が出るまで約2カ月ほどかかりますので、気長に待ちましょう。
・認定証書の発行
合否通知が届きます。晴れて合格していたら、指示に従いながら、認定手続きを行ってください。その後に認定証書が発行されます。晴れて遺品整理士の資格取得完了です。
3-3. 年収
遺品整理士の平均年収は約400~800万円程度です。つまり平均月収は約23~40万円程度になります。日本人の平均年収が348~613万円なので、遺品整理士になったら平均以上の給料が期待できると言えるでしょう。
3-4. 将来性
平均以上の給料が見込める遺品整理士は、社会の高齢化や核家族化が進む現代において、今後ますます需要が高まる可能性が高い職業だと言われています。
遺品整理に清掃・運搬・リサイクルは必須ですので、清掃会社、運搬会社、リサイクル業者なども事業拡大の副業として注目しています。「遺品整理士」の資格があることで、遺品整理の業界全体の健全化が図られ、将来的にも発展していくと予想されます。
4. きつい?遺品整理士の体験談
- 遺品整理士として働きはじめて最初の1カ月は現場に行くたびに辛い思いをして、作業に集中するのも大変でした。今でも故人の亡くなる直前の生活の様子を想像すると、気が重くなります。それでも、遺族の方に感謝されると頑張ろうって思えます。ー女性・20代
- ゴキブリが大量に足元を這い、死臭がたちこめている環境での運搬作業は堪えました。こういった現場はたまにあります。ー男性・30代
- 真夏の30度越えの炎天下、遺品整理の仕事はかなり危険で体力を消耗しました。遺族の方も急いでおり、スピード命の作業となったので、命がけでした。ー男性・40代
まとめ
いかがでしたか。遺品整理で求人募集を探す際の情報や、仕事選びで気をつけたいポイントなどをご紹介しました。ぜひ参考にしながら、自分に合う遺品整理業者を見つけてみてください。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。