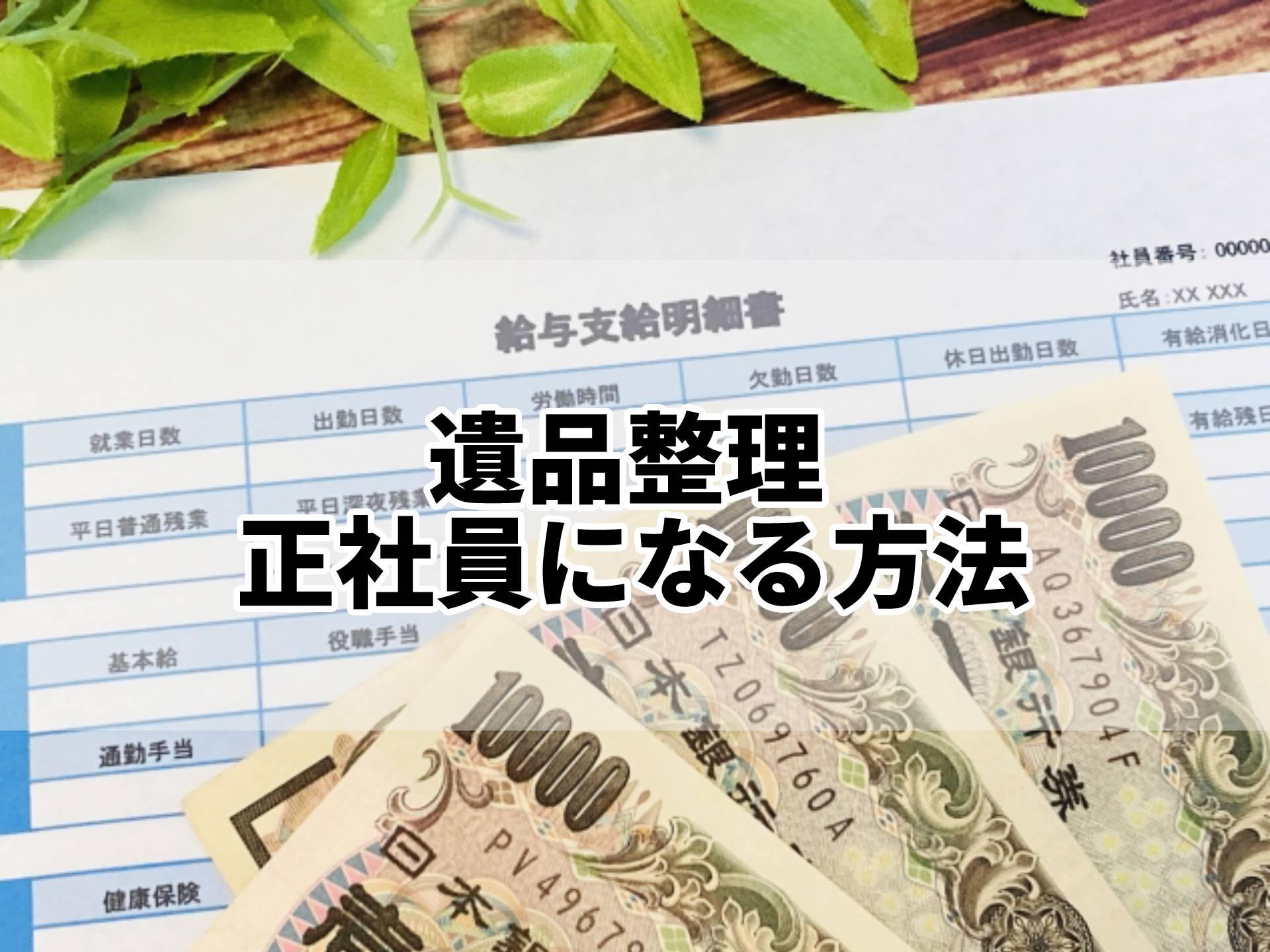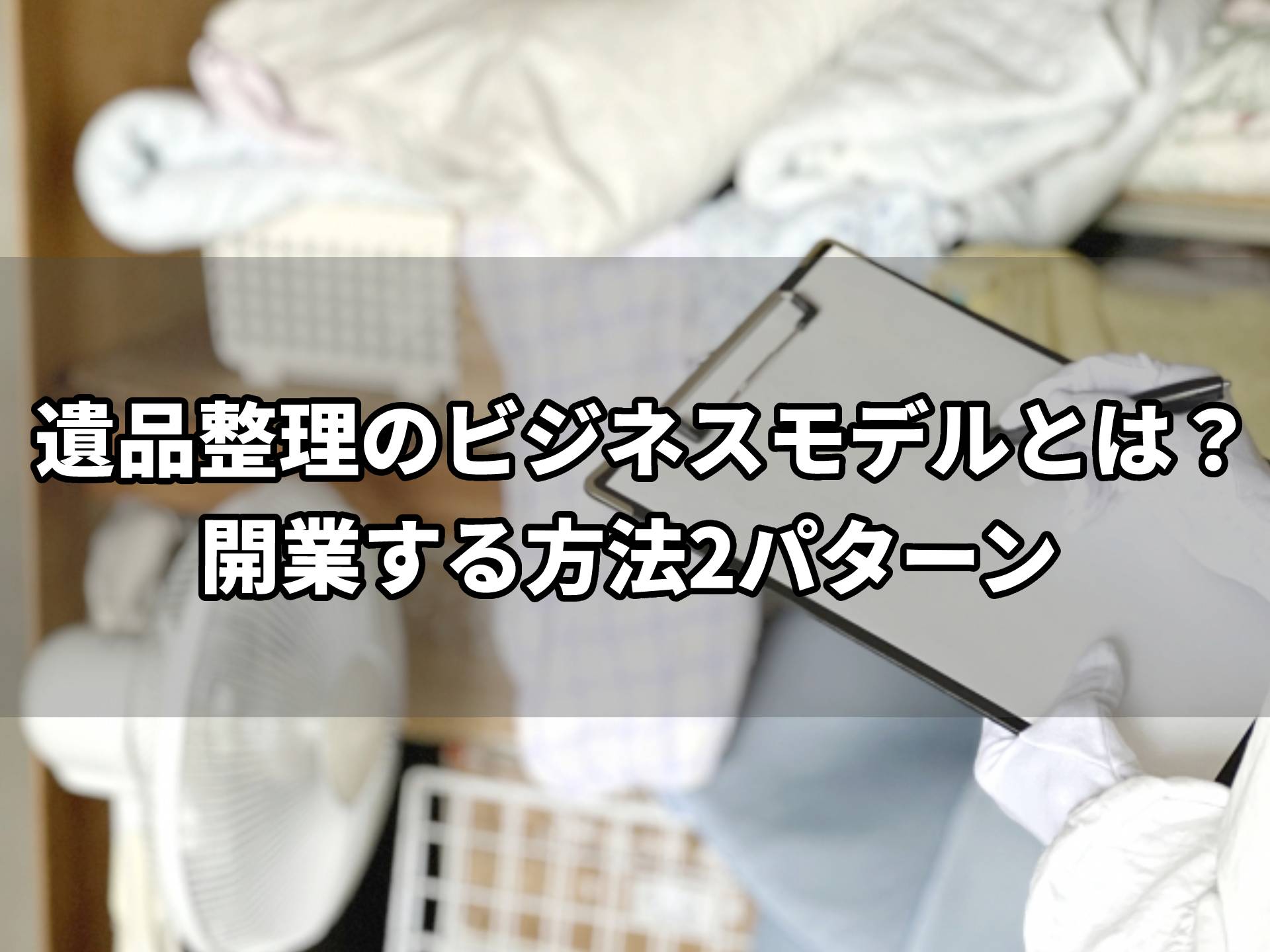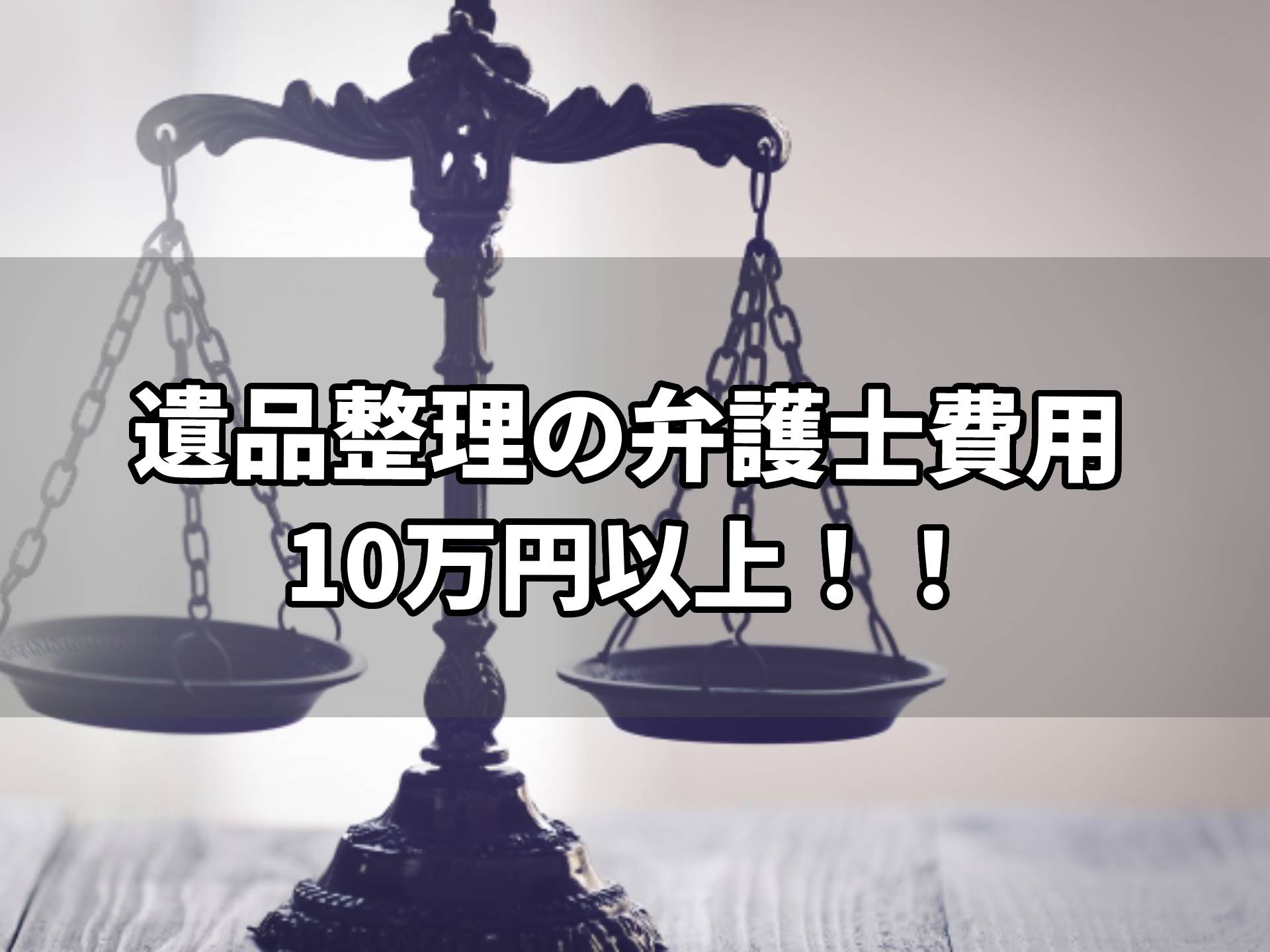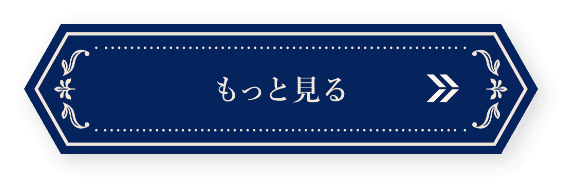遺品整理を行う4つのタイミング!いつから?どうやって?に答えます
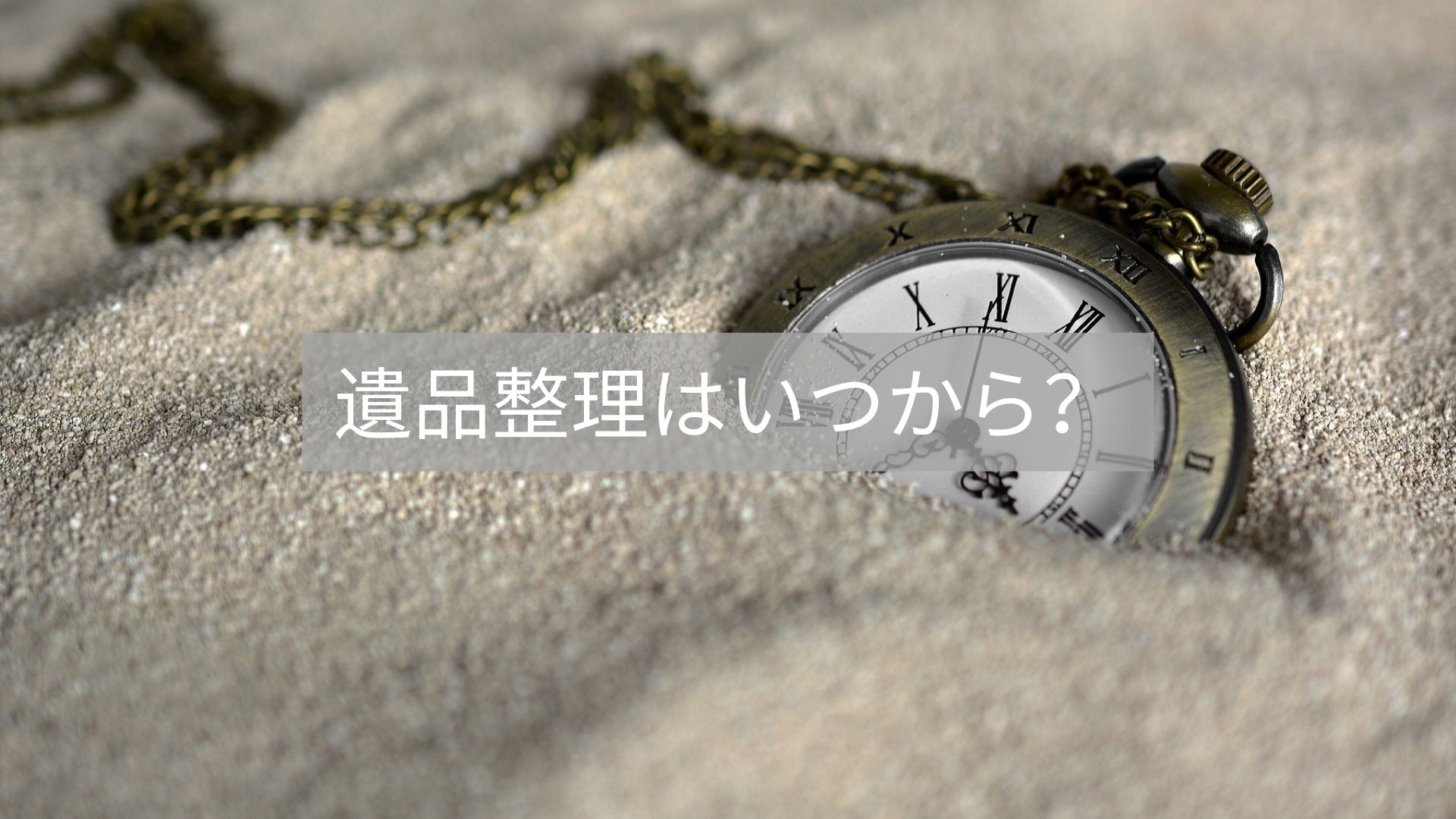
遺品整理をなかなかはじめられない…。
葬儀や諸々の手続きで忙しいなか、遺品整理に手をつけられない状況は十分に理解できます。そんな遺品整理はどのタイミングではじめるのが1番いいのか。賃貸か持ち家でタイムリミットがあったり、相続税が発する遺品があったりするので、まずは状況をしっかりと把握することが大切です。そういったことも含めて、遺品整理をいつはじめるべきかについて話していきます。
今回は、以下の内容でお送りします。
- 遺品整理をはじめるタイミング
- 遺品整理は自分のタイミングで
- 遅くはじめる遺品整理のデメリット
- 遺品整理の流れ
この記事を読めば、遺品整理をはじめるにあたってベストな時期や簡単な遺品整理の流れについて理解することができます。それでは見ていきましょう。
1. 遺品整理はいつからはじめる?4つのタイミング

まず、遺品整理をいつまでにやらなければいけないなどという決まりはありません。遺品整理の内容やかかる時間については特に正解はありません。人それぞれ状況がちがうため、期日がある方は期日までに、気持ちの整理がつかない方はゆっくりと行うことも可能です。そんななか、一般的に考えられる4つの遺品整理のタイミングをご紹介します。あくまで参考までにしてください。
- 49日を迎えた後
- 諸手続きの後
- 葬儀後すぐ
- 相続税の発生前
1-1. 49日を迎えた後
仏教では、故人の魂は死後から49日間までこの世をさまよっていると考えられています。そのため、魂が次の世へ旅立っていく49日を目安に遺品整理を行う方が多くいるでしょう。また遺族が集まりやすい機会のため、親族間で遺品整理や形見分けについて話し合いをしやすい場面でもあります。
1-2. 諸手続きの完了後
人が亡くなるとさまざまな手続きをする必要があります。死亡届をはじめ、電気や水道、ガス、年金、保険金などの手続きなどがあり、バタバタな日々を送ることになるでしょう。そのため、そういった必要な手続きが済んでからようやく遺品整理にとりかかるといった方も多くいます。
1-3. 葬儀後すぐ
故人が賃貸に住んでいた場合は、契約の問題が発生するため葬儀が終わってすぐに遺品整理を行う必要があります。また、遺族が遠方に住んでいて集まる機会が少ない場合にも、葬儀後すぐに遺品整理を行うことも多々あります。
1-4. 相続税の発生前
相続税とは、遺産を相続するときにかかる税金のことです。亡くなった方の遺した財産が、相続税の非課税額を超えていた場合、相続性の申告書を作成し、税務署に提出する必要があります。
申告書の提出期限は被相続人が亡くなってから10ヶ月以内に申告・納税しないといけません。この期間を過ぎてしまうと、相続税の控除を受けられなくなり、延滞税を課されてしまうことがあります。相続税を算出するためには、まずは遺品整理を行い、相続する財産の金額を調べることになります。現預金だけでなく、金銭的価値のあるものの査定、土地や不動産の評価額も調査する必要があるため、余裕のある遺品整理が必要です。
2. 遺品整理は自分のタイミングでOK

期日がある場合をのぞいて、遺品整理は基本的に自分の気持ちに整理がついたときに行うのがベストなタイミングといえます。前章で紹介した一般的な遺品整理のタイミングは効率的ではありますが、大切な故人の遺品はそう簡単に片づけることは難しいでしょう。精神的に落ち着いたあとに、思い出を振り返りながら行う遺品整理が理想かもしれません。1年以上遺品整理を行えず、放置しているケースも多くあります。時間に余裕がある場合はそれでかまわないでしょう。しかし、遺品整理を行うことによって気持ちの整理もつけやすくなるため、少しでも精神が安定したときに少しずつでもとりかかるのがおすすめです。
3. 遺品整理が遅いと発生する3つのデメリット

遺品整理は自分のタイミングで行うことがベストなタイミングとお話しましたが、長い期間放置していると金銭的に損をする可能性も考えられます。そのために遺品整理を遅く済ませた場合に起こりうる3つのデメリットを見ていきましょう。いつから、いつまでに遺品整理を行う必要があるのか、目処をたてるきっかけにもなります。
- 賃貸の場合
- 相続税が発生する場合
- 空き家の場合
3-1. 賃貸の場合
まずは、故人が賃貸に住んでいた場合、契約がどうなっているのか確認しましょう。賃貸契約が続いたままであると、退去までの家賃を払う必要があります。また、契約の解消を依頼した場合は、立ち除きの日が同時に遺品整理を終わらせなくてはいけない期日となるでしょう。
3-2. 相続税が発生する場合
親族が亡くなってから10カ月以内に申請・納税しなければ、相続税の控除を受けられなくなるため、延滞税を払う必要がでてきます。現預金だけでなく、金銭的価値のあるものの査定、土地や不動産の評価額も調査する必要があるため、余裕のある遺品整理が鍵となります。
3-3. 空き家の場合
故人が生前に住んでいた家を空き家のまま放置している場合は注意が必要です。もし空き家が特定空家に指定されると固定資産税が跳ね上がったり、50万円以下の過料が課される可能性があります。特定空家とは、空き家を長年にわたって放置し、有害になりうる場合に指定されます。
2015年5月26日に施行された空き家対策特別措置法によると、以下のいずれかの状態である空き家が特定空家と見なされます。
・そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
・著しく衛生上有害となるおそれのある状態
・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
4. これで安心!遺品整理は4ステップで

簡単に捨てることができなかったり、全く捨てることができないものもなかにはあります。急いで整理する必要があるからといって、全部廃棄してしまっては手遅れになることもあるでしょう。そこで代表的な遺品整理の方法を4つのステップで見ていきます。状況によって正しい遺品整理の手順や方法は異なりますが、あくまでひとつの代表的な流れです。ぜひ参考にしつつ、自分に合った流れを見つけてみてください。
- スケジュールを決める
- 分類する
- 分類したものを処分する
- 残した遺品の分配をする
4-1. スケジュールを決める
まずはスケジュールを立てましょう。いつまでに遺品整理を終わらせる必要があるのか、いつ作業ができるのかを考えるとスムーズに遺品整理を行うことができます。可能であれば、他の親族と話し合って作業を分担したり、遺品整理業者を利用する場合は手配をしたりと色々工夫ができます。しっかりと予定を立てるところから始めることがおすすめです。
4-2. 分類する
遺品は大きく分けて「残すもの」と「捨てるもの」の2つに分類できます。故人が生前に大切にしていた品や思い出の品などの形見になるもの、大事な書類や貴重品を残しておくことが何よりも重要です。また、貴金属や美術品など資産価値のある貴重品なども相続品として形見分けの対象にもなるため、慎重に分類する必要があります。
書類や貴重品リスト
通帳
クレジットカード、キャッシュカード
金
印鑑
身分証明書(パスポートなど)
健康保険証
契約書類
この他にも残しておいたほうがいいものは、リサイクルとして中古販売できる品です。再利用できるものは、買取業者や不用品回収業者に依頼したり、フリマアプリなどを利用したりして買い取ってもらいましょう。
リサイクル品リスト
大型の家電
小型家電
家具
衣服
金属類
4-3.捨てるものを処分する
残すものが判断できたら、それ以外は廃棄します。燃えるゴミや燃えないゴミは、自治体で決められた集積所へ持ち込んで処分します。自治体によって廃棄方法が異なることがあるため、廃棄する地域の自治体に確認しておきましょう。捨てるものの量によっては、買取業者や不用品回収業者に依頼することもひとつの手です。状況に応じて判断してください。
4-4. 残した遺品の分配をする
資産価値のある相続品は、平等に分配します。高価な宝石や芸術品、美術品などは、買取を行ったうえで分配ができます。また、価値の有無に関わらず、故人の想い出がある遺品は形見分けします。
形見品リスト
身に着けていたアクセサリー
衣類
趣味のコレクション
時計
書籍
これらは親族で分配することが一般的です。高価な遺品は、贈与税の対象になる場合があります。形見分けの相手の負担にならない遺品を選ぶようにしましょう。
まとめ
いかがでしたか。遺品整理をはじめるタイミングについて決めるために役立つ情報をご紹介しました。大切な人を失った後であるため、自分に負担がかからない時期行うことがベストでしょう。期日が迫っており、自らで遺品整理を行えない場合は、プロの遺品整理業者を利用することも考えられます。そちらもご検討ください。
弊社とらのこでは、遺品整理の際に出た不用品の買取を行っております。あらかじめ遺品の整理を行った後に再利用できる遺品があれば、捨てる前に買い取ることができます。
「こんなものも売れるの?」といった品があれば、まずはお気軽にご相談ください。
遺品の買取なら、とらのこ
とらのこでは、遺品を高価買取いたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。