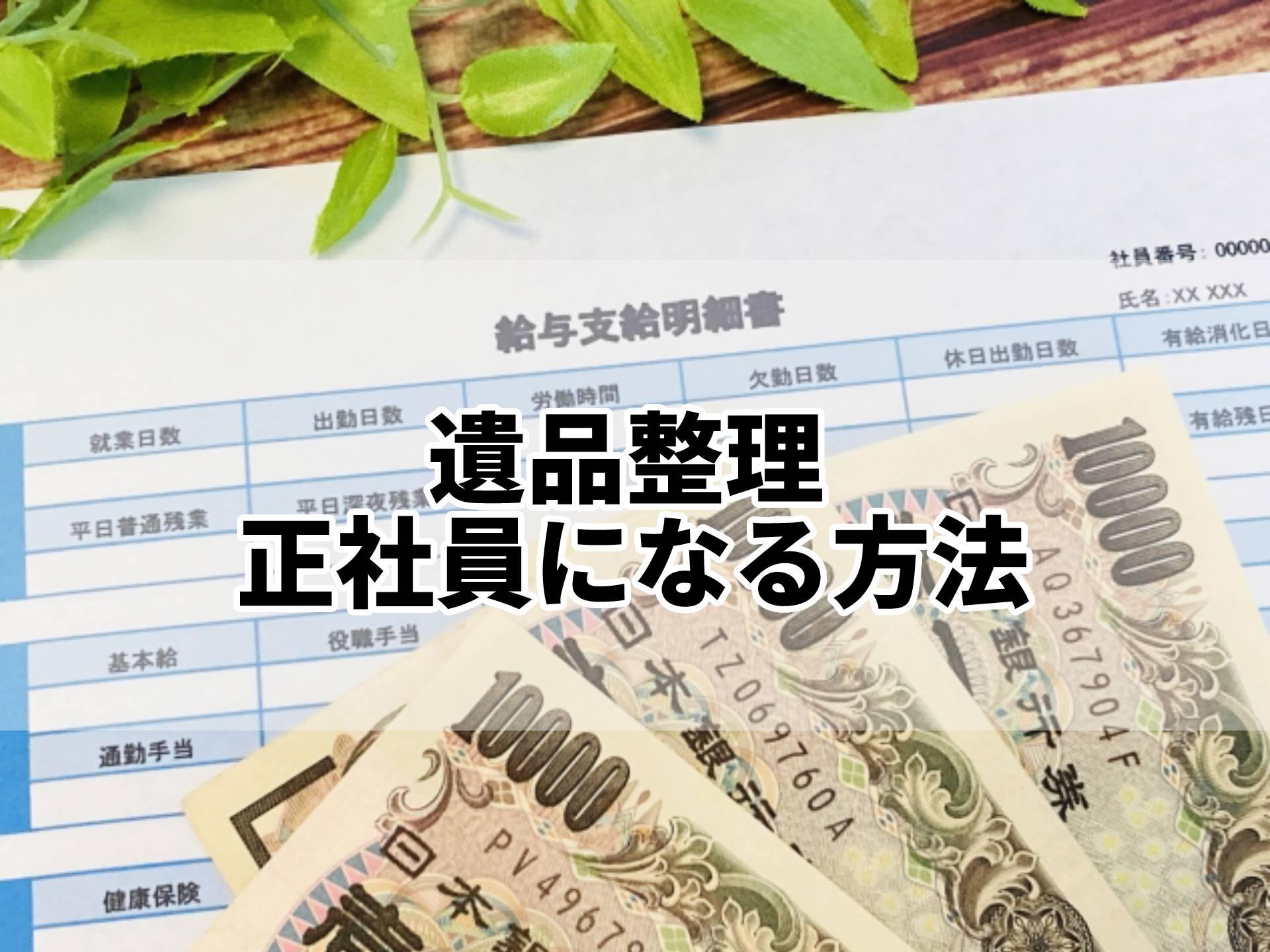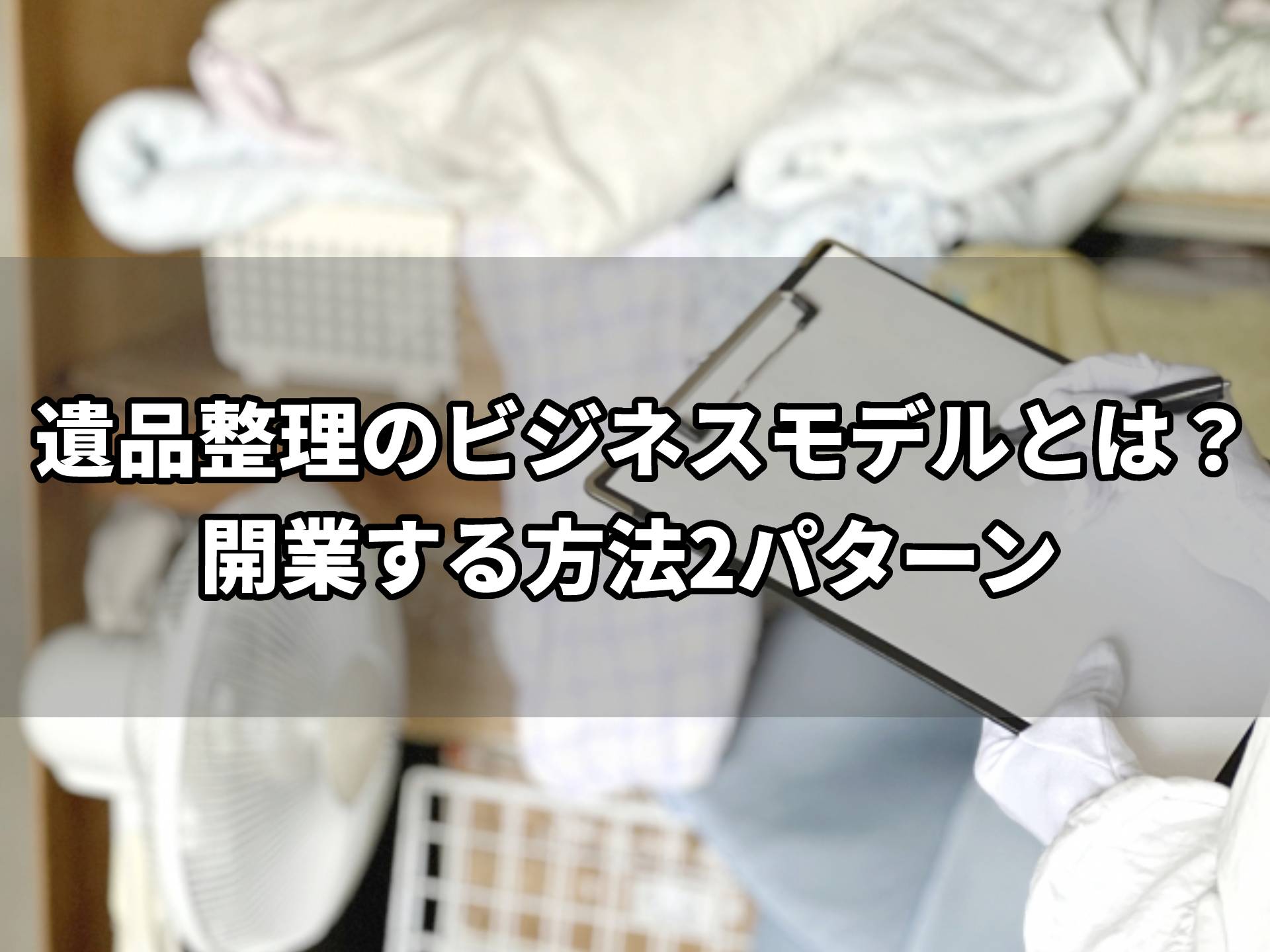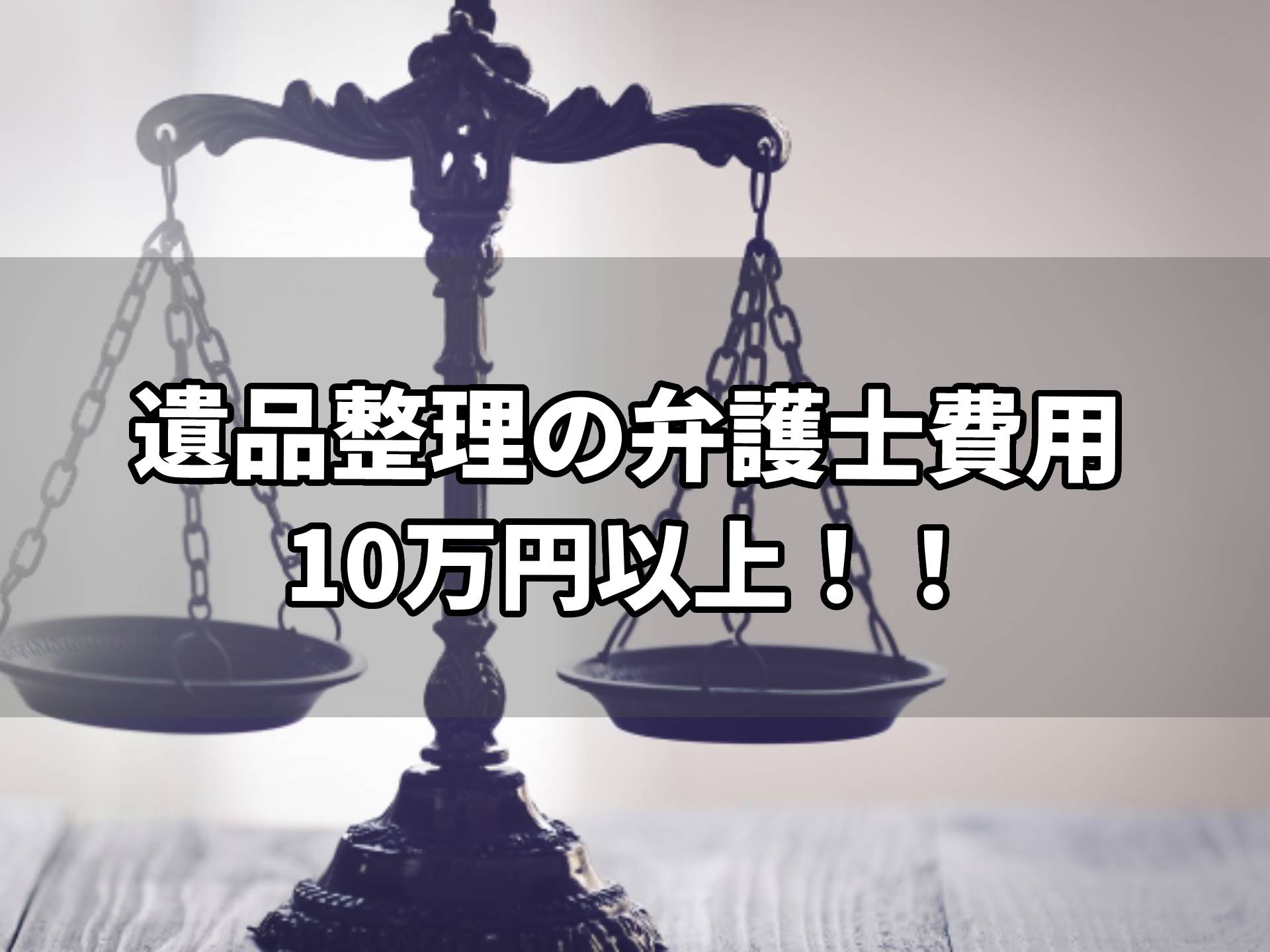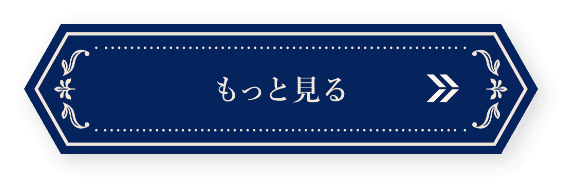遺品整理を自分でするノウハウを伝授!準備するモノと流れを徹底解説

愛する家族や親族が亡くなり、自分で遺品整理を行うことを検討していませんか?
何からスタートさせればいいのか分からず、作業が進まない場合もあるでしょう。
この記事では、遺品整理のノウハウや自分で行う際の準備物や方法と流れについて紹介しています。本記事を読むことで、ゴミ別の処分方法やメリット・デメリットも知ることが可能です。
参考にしてみてください。
1:遺品整理のノウハウ!自分で行う際の準備物
遺品整理のノウハウがない場合は、何から進めれば良いのか分からないこともあるでしょう。
自分で行う際は知識を得て、少しずつ用意を進めてみるのもおすすめです。
- 服装
- 用品
上記2つに分けて、遺品整理で必要になる準備物について紹介します。
1-2:自分で遺品整理を行う際の準備物
遺品整理を自分で行う際に、何を用意しておけば良いのでしょうか?
事前に必要な物が分かっていれば、準備もスムーズに進みます。
遺品整理を行う際の準備物を、服装も踏まえて一覧にしているので参考にしてみましょう。
| 準備物 | 詳細 | |
| 服装 | 軍手
汚れてもよい服 マスク 厚手の靴下 スリッパ |
スリッパはケガ防止対策用 |
| 用品 | ゴミ袋 | 自治体指定のものがあれば購入する
45〜70リットル程度が使用しやすい |
| ダンボール | 120サイズを多めに準備する
160サイズ(大きい荷物用)もいくつか用意する |
|
| ガムテープ | 布とクラフトテープのどちらでも問題ない | |
| ハサミ(カッター ) | 切れ味のよい物を人数分用意する | |
| 油性マジックペン | ダンボールの中身を書くために準備する |
2:効果的!遺品整理の方法と流れ
遺品整理を自分で行う場合の流れを知っていますか?
ある程度のノウハウを得ておくことで、作業もスムーズに進みます。
- スケジュールの計画
- 必要・不要な物の分別
- 不要な物を処分
- 遺品の分配
効果的な遺品整理の方法と流れを紹介します。参考にしてみてください。
2-1:スケジュールの計画
スケジュールの計画は、遺品整理を行う際になくてはならないものです。
計画をしっかりと立ててから作業を進めていき、スムーズに行いましょう。
終了予定日を決め、片付ける人数・遺品の量を把握して無理のない期間を設定してください。
作業内容も具体的に決めると目標ができるので、スピードも早くなります。
詳しくスケジュールの計画を立て、なるべく作業の負担を減らしましょう。
2-2:必要・不要な物の分別
遺品整理で出た物の分別は、慣れていないと難しく感じるでしょう。
仕分けがスムーズに行えるように、ノウハウを得ることがおすすめです。
必要・不要な物の分別を一覧にしましたので参考にしてみてください。
| 必要なもの | 不要な物(再利用・処分する物) |
| 財産・重要な書類・資産価値のある貴重品・通帳・クレジットカード・キャッシュカード・現金・印鑑・有価証券・身分証明書(パスポートなど)・土地の権利書・健康保険証・契約書類・貴金属・美術品 など | エアコン・洗濯機・冷蔵庫・テレビ・携帯電話・カメラ・パソコン・ベッド・タンス・鍋・釜・衣類など |
2-3:不要な物を処分
必要・不要な物を分別したら、不要な物を処分していきます。
自治体のゴミ出しルールを守り、燃えるゴミと燃えないゴミに仕分けして収集所へ運んで処分してください。
2-4:遺品の分配
故人の想い出がある物は、遺品の分配を行いましょう。
相手の負担にならない物を選び、芸術品・宝石・美術品などは買取を行ってから分配することも可能です。
高価な遺品は、贈与税の対象になることがあるので気をつけてください。
資産価値のある相続品は平等に分配することが大切になります。
故人の遺品として、着物・アクセサリー・ 時計 ・コレクション・書籍などが一般的に親族へ分配されます。
3:ゴミ別!処分方法を紹介
遺品整理で出た物は、どのように処分すれば良いのでしょうか?
分別方法のノウハウは難しく、自治体によって異なるので分からないこともあります。
ゴミ別の処分方法を一覧にしましたので参考にしてみてください。
| 再利用できる物 | 品目 |
| スチール缶やアルミ缶 | ジュースやお酒の缶、建築資材など |
| ガラス瓶 | 瓶、断熱材、建築・土木材料など |
| プラスチック | 再生トレイ、ゴミ袋、日用雑貨、化学製品の原料など |
| 家電 | 洗濯機水槽、金属部品など |
| 古紙 | 新聞紙、雑誌、段ボール、ティッシュペーパーなど |
再利用できる物は業者の無料引取や買取サービスを利用したり、自治体のゴミ回収のルールに沿って処分しましょう。
使用できる物はフリマアプリで販売したり、寄付するなどして遺品整理を行ってみてください。
| 意外と再利用できない物 |
| カバンや靴などの詰め物・食品の残りかすがついた紙
シールや粘着テープ・不織布 使い捨ておむつ・生理用品・ペット用トイレシート |
必要な物と再利用できる物以外は廃棄処分する物になります。
意外と再利用できない物の一覧も参考にしてみてください。
地域の自治体によって処分方法が違うので確認し、分別ルールを守って処分しましょう。
4:自分で遺品整理を行うメリットとデメリット
遺品整理を自分で行いたいけど、不安になることもあるでしょう。
気をつけることを知るだけでも、安心して取り組むことができます。
- メリット
- デメリット
自分で遺品整理を行うメリットとデメリットを紹介するので、参考にしてみてください。
4-1:メリット
自分で処分や掃除を行うと、業者を利用するための費用が節約できます。
遺品整理を行う際、作業量や不要な物の処分料、運搬費用・人件費などがかかり、まとまったお金の準備が必要です。
遺品整理を急いでいない方や時間がゆっくりととれる場合には、自分で遺品整理をした方が節約になるでしょう。
遺族だけで故人の思い出の物を整理したい方にとっても、大きなメリットといえるでしょう。
「故人の物を他人に触れられたくない、人目を気にせずに気持ちの整理をしたい」場合は、おすすめです。
4-2:デメリット
遺品整理は専門業者に依頼する場合に比べて、自分で行う場合は圧倒的に時間がかかります。
遺品の量が多く、大きい家なら整理や片付けの負担も大きくなるでしょう。
規模によっては年単位の時間が必要な場合もあるので気をつけてください。仕事面や費用面での負担がかかることも想定して計画を立てましょう。
騒音や異臭が発生すると、近隣トラブルに発展する場合があるのでデメリットといえます。
家の物を運んだり、不要な家具の解体を行うこともあるので近隣の方への配慮も必要です。
まとめ
遺品整理のノウハウや自分で行う際の準備物、方法と流れについて紹介しました。
自分で遺品整理を行う場合の流れを知ることで、計画的に作業を進めることができます。
ゴミ別の処分方法を参考にすることで、作業もスムーズに行えるでしょう。
メリットとデメリットもしっかりと把握した上で、遺品整理に取り組んでください。
遺品整理なら、とらのこ
とらのこでは、遺品整理をいたしております。
関連記事
遺品整理に関する、お役立ち情報を公開しています。